会社員が副業にはどのような税金がかかるのか、確定申告は必要なのかと不安に思う方は多いでしょう。副業収入は内容によって扱いが異なり、条件次第で税金の申告が求められます。
この記事では、副業に関わる税金の種類や申告の条件、手続きの流れを解説します。節税の方法も紹介しますので、ぜひ参考にしてください。
会社員が副業で納める必要がある税金

会社員が副業で収入を得た場合、本業の給与とは別に税金がかかります。副業に関係する代表的な税金は「所得税」「住民税」「個人事業税」「消費税」の4つです。これらの税金には課税基準や計算方法に違いがあるため、仕組みを理解しておきましょう。
所得税
所得税は、1年間の収入から必要経費や所得控除を差し引いた「所得」に対してかかる税金です。所得税は累進課税制度を採用しており、課税所得が大きいほど税率が高くなります。
会社員の場合、本業の給与は年末調整で処理されますが、副業収入があると確定申告で合算して申告しなければなりません。そのため、副業を始める際は収入と経費を正しく記録し、課税対象となる所得を把握しておくことが重要です。
住民税
住民税は、前年の所得に応じて課税される地方税です。市区町村に納める「市町村民税」「特別区民税(東京都23区のみ)」と、都道府県に納める「道府県民税」で構成されます。
住民税は、一律10%程度の税率で計算されるのが特徴。会社員の場合、本業の給与から自動的に天引きされる「特別徴収」が原則のため、副業分の住民税が本業分と一緒に徴収される場合もあります。
個人事業税
個人事業税は、事業として継続的に行う副業が対象となり、一定の所得を超える場合に課税される税金です。課税の対象となる業種は70種類以上あり、代表的なものは物販・デザイン・プログラミング・翻訳・ライティングなどです。
個人事業を対象としているため、給与所得や一時的な収入には課税されません。課税額は「事業所得-290万円(基礎控除)」に税率(3〜5%)をかけて計算されます。
副業にかかるケースはまれですが、軌道に乗れば関係してくるので、頭の隅に入れておきましょう。
消費税
消費税は、非課税や免税を除く国内取引に広く課される税金です。副業でも、事業として商品やサービスを継続的に提供する場合は対象となります。
原則として、前々年の課税売上高が1,000万円を超えると課税事業者となり、消費税の申告・納付が必要です。売上規模が小さい場合でも、適格請求書発行事業者に登録(インボイス登録)すれば消費税の納税義務が生じます。
インボイス登録は今のところ任意なので、登録するかどうかは慎重に決めましょう。

副業で確定申告が必要になる条件

本業の所得は年末調整で処理されますが、副業で得た収入については条件によって確定申告が必要になります。
「20万円ルール」と呼ばれる基準や、収入の種類による違いは理解しておかないと、申告漏れにつながるため注意しましょう。ここでは、確定申告が必要になる具体的な条件を解説します。
20万円ルールとは
副業の確定申告でよく聞かれるのが「20万円ルール」です。これは、副業の所得(収入から必要経費を差し引いた金額)が年間20万円以下であれば確定申告は不要、という確定申告のルールを指します。
ただし、この20万円ルールは所得税に限った話です。住民税については少額でも申告が必要になるため、「20万円以下だから」と何もしないでいると追徴課税を求められるかもしれません。
また、医療費控除や住宅ローン控除を利用するために確定申告を行う場合は、副業収入が20万円以下でも申告が必要です。20万円ルールは損にも得にもつながるので、正しく離開しておきましょう。
申告が必要な所得の種類
副業の収入は内容によって「所得の種類」が異なり、申告の要否も変わります。所得税の対象となる「課税所得」は10種類あり、副業になりやすいのは以下の4つです。
- 給与所得
-
アルバイトやパートなど、雇用契約に基づく収入。本業以外の給与所得がある場合は、原則すべて確定申告が必要です。
- 事業所得
-
ライター・デザイナー・プログラマーなど、規模や反復性がある収入。年間所得が20万円を超えると申告が必要です。
- 雑所得
-
副業の規模が小さく、事業としての継続性が認められない収入。ハンドメイド作品をECサイトで販売する、ポイ活などが該当します。年間所得が20万円を超えると申告が必要です。
- 不動産所得
-
賃貸物件などから得る収入。金額にかかわらず確定申告が必要です。
給与所得や不動産所得は少額でも申告が必要な所得もあれば、事業所得や雑所得のように20万円ルールが適用される所得もあります。副業の内容に応じて、区分を正しく判断することが大切です。
会社員が副業をする際の注意点
会社員が副業を行う際には、税金の申告だけでなく勤務先への影響も考えましょう。就業規則で副業が禁止されている場合、無断で行うと減給・降格・解雇などの対象になる可能性があります。
会社員の住民税は特別徴収されているため、収入が増えることで会社に知られてしまいます。隠してリスクを負うよりも、避けられるリスクは避けるのが懸命な判断です。
税務関係で会社に負担をかけさせたくない場合は、確定申告で副業分の住民税を「普通徴収」にしましょう。

副業が給与所得の場合の確定申告

会社員の税金は勤務先が年末調整を行うため、確定申告をする必要はありません。同じ給与所得なら副業分も本業で処理してもらえそうですが、副業分に関しては確定申告が必要です。
ここでは、年末調整と確定申告の違い、給与所得の確定申告に必要な書類を解説します。
年末調整と確定申告の違い
年末調整と確定申告はいずれも税金を納める手続きですが、対象や方法が異なります。年末調整は会社員の給与に対して勤務先が代行するもので、毎月の源泉徴収額と実際の税額との差を精算する仕組みです。
一方の確定申告は、1年間の所得を自分で計算し、税務署へ申告する手続きです。本業以外の収入は年末調整で処理できないため、副業をしている場合は確定申告が必要となります。
また、医療費控除やふるさと納税などの控除も年末調整で処理できないため、副業をしていなくても確定申告が必要です。
給与所得の確定申告に必要な書類
給与所得の確定申告に必要となるのが「源泉徴収票」と「確定申告書」です。副業がアルバイトやパートの場合、どちらの給与も源泉徴収されているので、本業と副業、両方の源泉徴収票を用意しましょう。
確定申告書は、給与などを書き込む確定申告の本書です。会計ソフトで作成するほか、国税庁のWebサイトからダウンロードする方法もあります。確定申告書を作成し終えたら、e-Taxや郵送を使って期限までに提出しましょう。

確定申告から納税までの流れ

副業の収入が事業所得・雑所得・不動産所得に該当する場合は、年末調整で処理されないため、確定申告を行わなければなりません。
ここでは、書類の準備から納税まで流れを解説します。
申告に必要な書類と帳簿の準備
事業所得・雑所得では、経費が発生する場合もあります。確定申告は所得(収入から経費を引いた金額)を申告するものなので、収入と経費それぞれの金額を明確にしなければなりません。
収支を帳簿で記録し、領収書・請求書・振込明細などを適切に保管します。帳簿の書き方は、青色申告であれば複式簿記、白色であれば単式簿記です。不動産所得も同様に、家賃収入や修繕費などの支出を記録する必要があります。
これらを基に「収支内訳書」や「青色申告決算書」を作成し、最終的に確定申告書に反映させます。
e-Taxでの申告方法
確定申告は、e-Tax・郵送・窓口のいずれかで提出できますが、便利かつスピーディーな「e-Tax」がおすすめです。青色申告の65万円控除を受けるにはe-Taxでの提出が必須になるので、e-Taxでの流れをマスターしておきましょう。
まず、マイナンバーカード方式かID・パスワード方式を選び、利用者識別番号を取得します。その上で国税庁の「確定申告書等作成コーナー」にアクセスし、収入や経費の金額を入力して申告書を作成します。
添付書類などがあれば添付し、問題なければ送信しましょう。提出が完了すると受付結果が通知され、控えとして保存できます。

納税方法と住民税の特別徴収
確定申告後、納める税金がある場合は期限までに納税を行います。
所得税の主な納付方法は、金融機関やコンビニでの納付、口座振替による振替納税、インターネットバンキングです。口座振替を選べば手続きの手間が少なく、納め忘れの防止にもつながります。
住民税は本業の給与から天引きされる「特別徴収」が基本ですが、確定申告で「普通徴収」を希望すれば副業分だけ自分で納付となります。納付書が届いたら、コンビニや金融機関で納付しましょう。
個人事業税が課税される場合は、年2回に分けて納付書が届きます(自治体によっては一括)。こちらも期限内に納付しましょう。
事業所得が一定額を超える場合は「個人事業税」も課税されます。これは都道府県税で、年2回に分けて納付する形が一般的です。
インボイス登録をした人は、消費税も納付します。消費税は原則として年1回、確定申告と合わせて申告・納付を行います。

会社員の副業に役立つ節税対策

副業収入が増えると、その分税金の負担も大きくなります。しかし、確定申告を正しく行い、制度を活用すれば節税は可能です。ここでは、会社員の副業でもできる節税対策を解説します。
青色申告で特別控除を受ける
確定申告には「青色申告」と「白色申告」の2つの方法があり、節税効果が高いのは「青色申告」です。青色申告は複式簿記による帳簿付け、電子申告などの条件を満たすことで、最大65万円の青色申告特別控除を受けられます。
白色申告は帳簿作成の手間が少なくなりますが、青色申告特別控除のような控除は受けられません。
手間がかかっても65万円の控除を受けたほうが金銭的な負担は軽くなるので、安定した収益を出している場合は青色申告を選択しましょう。

経費を計上する
「副業では経費が認められない」と思っている人もいるかもしれません。給与所得の場合は経費計上できませんが、事業所得や雑所得では通常の個人事業主と同じように経費を計上できます。
経費として認められるのは、仕事用に購入したパソコンやソフト、消耗品費などです。家賃や光熱費、通信費なども、プライベートでの利用分を除いた「事業分」であれば経費として認められます。
経費にするには領収書・レシートの保管が必須になるので、帳簿と一緒にしっかりと管理しましょう。
ふるさと納税や医療費控除を組み合わせる
副業による税負担を抑える方法として、ふるさと納税や医療費控除などの制度を活用するのもおすすめ。
ふるさと納税は、寄付した金額のうち2,000円を超える部分が所得税や住民税から控除され、実質的な負担を抑えながら地域の返礼品を受け取れる制度です。
医療費控除は、年間の医療費が10万円を超えた場合に申告できる所得控除です。治療代や治療に伴う医薬品代、妊娠時の定期検診、出産時の入院費用、不妊治療に伴う費用も対象となります。
これらの控除制度を上手に活用し、トータルの税負担を軽減させましょう。
申告漏れや遅延があると税負担が増える!
副業収入を正しく申告しなかったり、確定申告の期限に遅れたりすると、追徴課税の対象となり税負担が増えてしまいます。
申告を忘れた場合は「無申告加算税」、期限までに納付できなければ「延滞税」が課されます。さらに、意図的に収入を隠したと判断されると「重加算税」が課される可能性も。
これらのペナルティは副業の収益だけでなく、生活を圧迫するため、確定申告や住民税の申告は期限内に必ず行うようにしましょう。

まとめ|会社員の副業にかかる税金は確定申告で申告しよう!
会社員の副業も、所得税・住民税・個人事業税・消費税といった税金の仕組みを正しく理解することが大切です。
中でも所得税と住民税は多くの人が関係するものなので、「20万円ルール」をはじめとした確定申告のルールをしっかり覚えておきましょう。
税負担を減らすには、青色申告を使う、ふるさと納税や医療費控除などを活用するなどの方法があります。「副業をやっててよかった」と思えるように、しっかりと対策をしてくださいね。

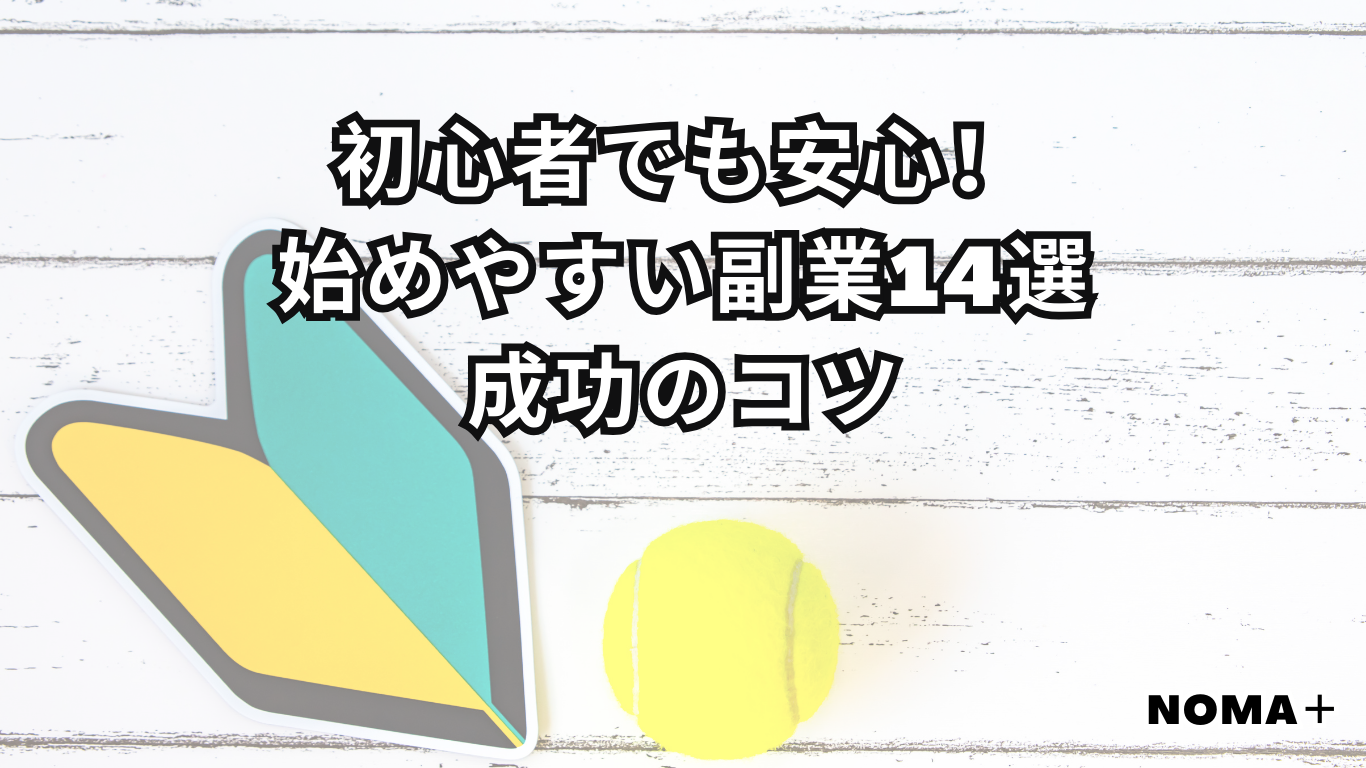











コメント