会社員は年末調整されるため、副業をしても確定申告が必要ないと感じるかもしれません。しかし、年末調整にはルールがあり、副業先で源泉徴収されていたとしても確定申告が必要になるケースがあります。
この記事では、年末調整と確定申告の違い、確定申告が必要なケースを解説します。確定申告に必要な書類や確定申告書の作成方法も紹介しますので、ぜひ参考にしてください。
年末調整と確定申告の概要

副業をする会社員は、年末調整と確定申告の違いを理解しておくことが大切です。両者の仕組みを正しく知ることで、自分にどの手続きが必要なのか判断でき、正しく所得を申告できるようになります。はじめに、年末調整の仕組みと確定申告との違いを解説します。
年末調整の仕組みと対象者
年末調整は、会社員やアルバイトなどの給与所得者に対し、勤務先が行う税金の精算手続きです。
毎月の給与からは源泉徴収として概算の所得税が差し引かれますが、その金額は1年間の収入や控除額を正確に反映していません。年末に1年間の所得や各種控除を計算し直し、払いすぎた税金は還付、不足分を追徴します。
年末調整ができるのは原則として1つの勤務先のみのため、複数の会社から給与を受け取っている場合は確定申告で最終調整が必要となります。
確定申告との違い
年末調整と確定申告は、いずれも1年間の所得税を正しく計算するための制度ですが、誰が手続きをするのか、どこまでを対象にするのかが違います。
年末調整は雇用者(勤務先)が行うもので、1か所から得ている給与所得を対象に源泉徴収した所得税を精算します。
一方の確定申告は、事業主や副業をする会社員、年金受給者などが自ら所得を申告する手続きです。このほか、医療費控除や寄附金控除、ふるさと納税などの控除申請の役割もあります。
本業の給与だけなら年末調整で済みますが、それ以外の収入があるときは会社員も確定申告が必要です。
副業は年末調整で勤務先に見つかるのか
年末調整はあくまで本業の給与に関する所得税を精算するもののため、年末調整をしたことで副業が本業の会社に知られる可能性は基本的にありません。
しかし、年末調整が行われた翌年に住民税が課税されることで発覚するケースがあります。この理由は、給与所得者の住民税が給与から天引きされている(特別徴収)からです。
企業は自治体に「給与支払報告書」を提出しなければならず、報告の対象は正社員・アルバイト関係なく、給与を支払うすべての雇用者です。副業により所得が増えれば住民税も増え、合算の住民税を自治体が会社に通知することで副業が知られます。
副業が給与所得・雑所得・事業所得どの場合も、副業分の住民税は原則として本業の給与から合算で差し引かれます。一時的であれば隠れて副業をできるかもしれませんが、いずれはバレると思ったほうがよいでしょう。
副業で確定申告が必要なケース

年末調整は本業の給与所得だけを対象とするため、仕組みを考えると副業をしていれば確定申告をしなくてはならないことになります。
しかし、確定申告には条件があるため、副業をしているすべての会社員が対象になるわけではありません。ここでは、確定申告が必要になるケースを解説します。
年間所得が20万円を超える場合
副業をしている会社員は、年間の副業所得が20万円を超えると確定申告が必要になります。「所得」は収入から経費や控除を差し引いた金額のことを指すので、「受け取ったお金=所得」ではありません。
給与所得の場合、収入から給与所得控除を差し引いた後の金額が20万円を超えれば対象になります。雑所得や事業所得の場合は、収入から経費を引いた金額で判断します。
副業をする会社員の確定申告は、どのような所得区分であっても「副業で得た1年間の所得が20万円以上あれば必要」と覚えておきましょう。

20万円以下でも確定申告をした方がよいケース
副業の年間所得が20万円以下であれば、原則として確定申告は不要です。しかし、医療費控除や寄附金控除(ふるさと納税)、住宅ローン控除などの各種控除を受けたい場合は、所得金額に関係なく確定申告が必要になります。
また、副業先で源泉徴収されている場合も注意が必要です。年間所得が20万円以下であっても、払いすぎた所得税を取り戻すには確定申告を行う必要があります。副業の金額が少ない場合でも、控除や還付を受けたいときは必ず申告を行いましょう。
年末調整後に確定申告をする手順【副業の源泉徴収あり】

副業先から給与を受け取り、源泉徴収されている場合は、その源泉徴収票を基に確定申告を行います。ここでは、源泉徴収されている場合の確定申告に必要な書類、確定申告書の記入方法を解説します。
必要書類
副業先から給与を得ている場合は、本業と副業、両方の「源泉徴収票」を用意しましょう。源泉徴収票とは、年間の給与額と源泉徴収された所得税額が記載されたもので、毎年12月から翌年の1月にかけて発行されます。
源泉徴収されている場合の確定申告は、基本的に源泉徴収票のみで完結するため、医療費控除や寄附金控除などを申請しない限りこれ以上用意する書類はありません。

確定申告書の作成方法
給与所得の確定申告では、確定申告書の「収入金額等」と「所得金額等」それぞれの「給与」の欄に金額を記入します。それぞれの源泉徴収票金額を合算し、年間の給与所得を申告する形です。
記入する主な項目は「支払金額」「源泉徴収税額」「給与所得控除後の金額」で、源泉徴収票に記載された内容をそのまま転写すれば問題ありません。なお、控除を利用する場合は、医療費や寄附金などの金額もあわせて記入します。
国税庁が提供する「確定申告書等作成コーナー」を利用すれば、源泉徴収票の内容を入力するだけで自動的に計算されるため、初心者でも安心して手続きできます。
年末調整後に確定申告をする手順【副業の源泉徴収なし】
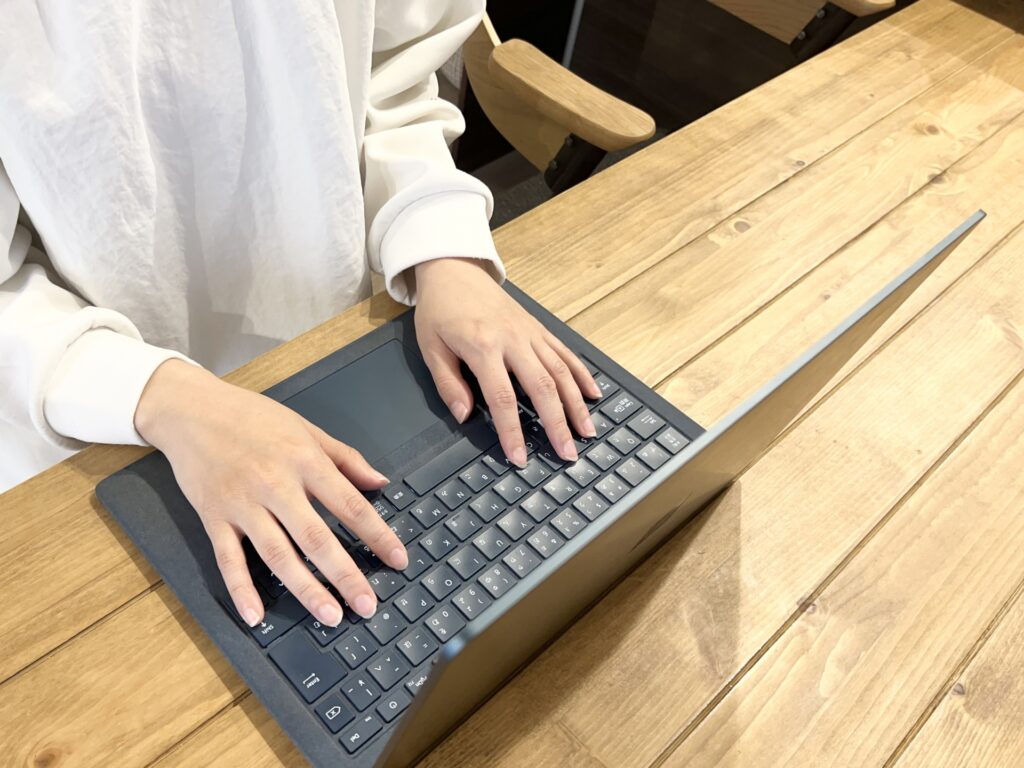
副業で源泉徴収されていない場合は、収支をまとめた上で確定申告を行います。源泉徴収されない副業は、業務委託や少額のアフィリエイトなどの「雑所得」「事業所得」が該当します。
ここでは、源泉徴収されていない場合の確定申告に必要な書類、確定申告書の記入方法を見てみましょう。
必要書類
雑所得・事業所得に該当する場合は、本業の源泉徴収票、年間取引をまとめた帳簿が必要です。帳簿をを基に確定申告書を作成するため、日々の取引内容を正確に記録しておかなくてはなりません。
また、誰から報酬を受け取ったのかを報告しなくてはならないため、報酬明細書など取引先の名前・住所がわかる書類も必要です。
帳簿を作成するには、報酬明細書や発注書・請求書、領収書など取引を証明するものが必要になります。領収書は紙やデータがなければ無効となり、経費計上できなくなるため注意しましょう。

確定申告書の作成方法
雑所得や事業所得の確定申告では、収入・所得ともに「雑→業務」または「事業→営業」の欄に金額を記入します。
帳簿でまとめた年間の収入から経費を引いて所得金額を算出し、それぞれを指定の欄に記入しましょう。本業の給与に関しては、源泉徴収票を見ながら収入・所得の「給与」にそれぞれ金額を記入し、源泉徴収税額も記載します。
雑所得・事業所得は確定申告書のほかに「収支内訳書」や「青色申告決算書」を作成する必要があります。収支内訳書は白色申告、青色申告決算書は青色申告に必要になり、青色申告は事業所得でしか選べないため注意しましょう。
なお、副業が雑所得や事業所得の場合は、副業分の住民税を自分で納付するか、本業の給与から天引きするかを選べます。自分で納付する場合は、確定申告書第二表にある住民税の項目で「自分で納付」に◯をつけましょう。

確定申告をしない場合は住民税の申告が必要
副業の所得が20万円以下で確定申告を省略できる場合でも、住民税については別途申告が必要です。住民税は所得税とは異なり、金額にかかわらず所得があれば課税対象となるためです。
申告は自治体の役所や税務課で行い、前年の副業収入や経費を記載した書類を提出します。特に副業先から源泉徴収票が発行されない場合は、自分で収入を申告しなければなりません。
申告を怠ると後から修正を求められたり、延滞金が発生したりする可能性があるため注意が必要です。確定申告をしない場合でも、住民税の申告は必ず行いましょう。

年末調整後の確定申告で注意すること

副業をしている会社員が確定申告を行う際には、期限や申告内容に関する注意点を押さえておくことが大切です。
うっかり忘れたり誤って手続きをしたりすると、思わぬアクシデントにつながります。ここでは、年末調整後に確定申告を行う際に注意したいポイントを解説します。
期限までに必ず行う
確定申告は、原則として翌年の2月16日〜3月15日の間に行わなくてはなりません。この期限を過ぎてしまうと、延滞税や無申告加算税が課される可能性があり、余分な負担につながります。
また、申告が遅れると還付金の受け取りも先延ばしになってしまいます。副業をしている会社員にとって、年末調整後の確定申告は必須の手続きです。
提出方法は税務署への持参や郵送のほか、e-Taxを利用したオンライン申告も可能です。どの方法で申告する場合も、早めに準備を始め、期限内に手続きを終わらせましょう。
2カ所で年末調整をしたら必ず修正する
年末調整は本来1カ所の勤務先でしか行えませんが、誤って副業先でも年末調整を受けてしまうケースがあります。両方の勤務先で所得税の精算が行われると正しい所得税額が算出されず、払いすぎたり、足りなくなったりしてしまいます。
本業と副業それぞれで年末調整を受けた場合は、確定申告を行い、正しい所得税額に修正しましょう。修正を怠ると税務署から指摘を受けたり、追徴課税の対象になったりする可能性があります。
雑所得・事業所得の人は帳簿をつける
雑所得や事業所得は、日々の収入や経費を帳簿に記録することが義務付けられています。帳簿は確定申告書を作成する際の基礎資料となるため、正確に記録しておくことが重要です。
記録が不十分だとお金の動きと帳簿が一致せず、正しく申告できなくなります。手作業で帳簿をつけるのが大変だという方におすすめなのが、クラウド型の会計ソフトです。
会計ソフトは銀行口座やクレジットカードと連携し、取引が行われると自動的に仕訳をしてくれます。AI機能が搭載されているものであれば、より効率的に作業できるでしょう。
\おすすめの会計ソフト/
まとめ|副業をしている会社員は年末調整後に確定申告をしよう!
会社員が副業をしている場合、本業分は年末調整で精算されますが、副業分については確定申告で精算が必要になります。ただし、副業の年間所得が20万円以下の場合は確定申告をする必要はないため、自分が確定申告の対象になるのかを明確にしておきましょう。
確定申告は、期限を過ぎると追徴課税のペナルティが課されます。確定申告をスムーズに進められる良い、必要書類を早めに用意しておく、会計ソフトで帳簿作成効率化を図るなどの工夫をしましょう。












コメント