「ブログはもうオワコンなのでは?」と不安に感じていませんか。確かにSEOの難化やSNSの普及など対策すべき課題はありますが、ブログには今も成長の余地があります。
この記事では、オワコンといわれる理由と実情、伸びるブログの特徴、AI時代に成果を出すための戦略を解説します。
ブログがオワコンといわれる理由
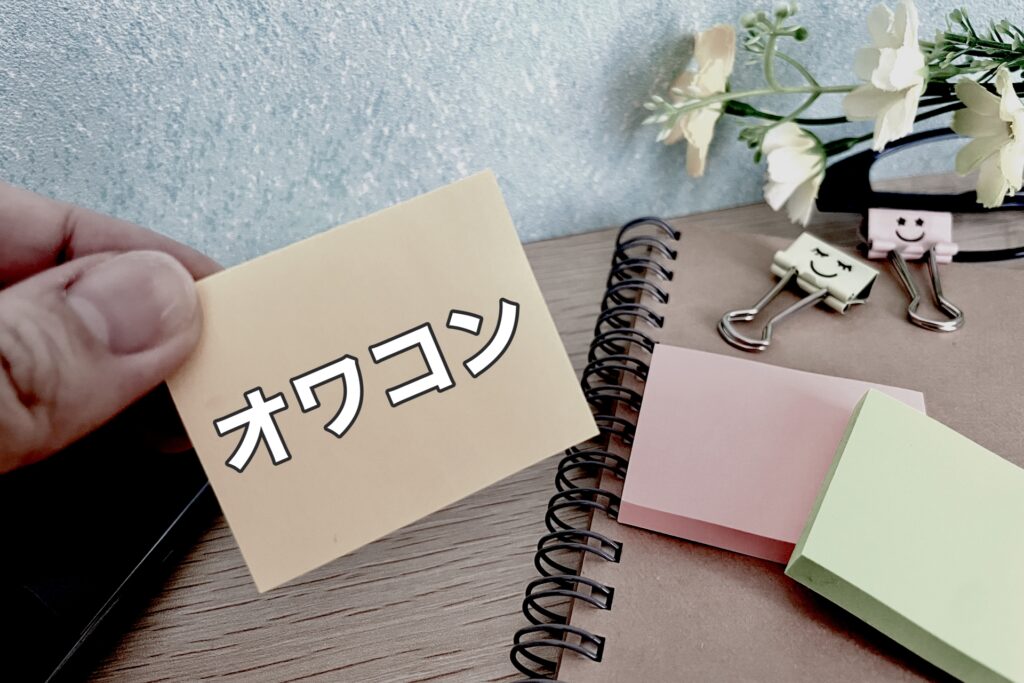
「ブログはもうオワコン」とよく耳にしますが、その背景には確かな理由があります。検索エンジンの仕組みが複雑化し、動画やSNSが主流となり、さらに企業メディアの参入で競争が激化しました。
ここでは、多くの人がブログを時代遅れと感じる具体的な理由を解説します。
SEO対策が難しくなり上位表示しづらい
記事を量産するだけで上位表示された時期もありました。しかし、現在はGoogleのアルゴリズムが高度化し、検索で評価される基準が大きく変わっています。
その中でも重視されるのが「E-E-A-T(経験・専門性・権威性・信頼性)」です。企業サイトや専門家が発信する記事は権威性や信頼性を示しやすいのに対し、個人ブログは実績や裏付けを示しにくく、評価を得にくい傾向があります。
それにより安定して上位に入りにくくなり、さらにコアアップデートによって順位が大きく変動するようになったのです。こうした状況から「ブログはオワコン」といわれています。
動画やSNSの台頭でユーザー行動が変化
YouTubeやTikTokなどの動画プラットフォーム、TwitterやInstagramといったSNSが普及したことで、ユーザーの情報収集スタイルは大きく変わりました。
文字中心のブログを読むよりも、短時間でわかりやすく情報が得られる動画やSNS投稿を好む人が増えています。若い世代ほどSNSを使って調べ物をする傾向が強く、ブログのアクセス減少にもつながっています。
拡散性の高いSNSは新しい情報が瞬時に広がるため、スピード感が低いことも「ブログはオワコン」といわれる理由です。
企業や法人メディアの参入による競争激化
近年、ブログ市場へ企業や法人が積極的に参入するようになりました。大手企業が運営するオウンドメディアは、豊富な資金力を活かして専門ライターを起用し、記事の質や更新頻度で個人ブログを大きく上回ります。
また、企業サイトはブランド力や信頼性によりE-E-A-Tの評価を得やすく、検索上位に表示されやすい傾向があります。その結果、同じテーマで戦う個人ブロガーは露出が難しくなり、収益が伸び悩むようになりました。こうした企業メディアとの競争激化も、「ブログはオワコン」といわれる要因のひとつです。

ブログ運営は厳しくなっているもののオワコンではない!

競争が激しくなり「ブログはオワコン」といわれがちですが、実際には依然として成長を続けています。インターネット広告市場の拡大や個人ブログならではの信頼性、テキスト情報への安定した需要などがその理由です。
ここでは、ブログがオワコンではない理由を解説します。
インターネット広告市場は拡大傾向にある
インターネット広告費は年々増加しており、企業がWeb上での集客や販売に力を入れる状況が続いています。この拡大傾向はブログにとっても追い風です。
検索やSNSを経由してブログに訪れるユーザーは購買意欲が高い傾向にあるため、広告やアフィリエイト収益が見込めます。広告収入の仕組みが以前より整備されたこともあり、ASPに登録すれば初心者も収益化しやすくなりました。市場が拡大している限り、ブログは収益源として十分に機能し続けるでしょう。
個人ブログは読者に信頼されやすい
企業サイトや大規模メディアは情報量が豊富にあるものの、「宣伝目的ではないか」と感じさせる場合もあります。一方の個人ブログは、筆者の体験や実感を交えた発信が中心のため、宣伝目的と思われることは基本的にありません。
実際にサービスや商品を使った感想、失敗から得た学びなどは共感を呼びやすく、信頼性につながります。専門分野や特定ジャンルに特化した個人ブログは、読者から「同じ目線で答えてくれる存在」として支持されやすいですよ。
テキスト情報は依然として検索需要が高い
動画やSNSが主流になったとはいえ、検索エンジンで探されるのは今もテキスト情報が中心です。文章は情報を体系的に整理できるため、複雑な内容や正確性が求められるテーマを理解するのに適しています。
特に医療・金融・法律などの分野では、根拠を示しながら丁寧に説明された記事が重宝され、テキスト情報の需要は依然として高いままです。また、検索エンジン自体もテキストを基盤に評価する仕組みのため、テキストを中心とするブログは今後も重要な役割を果たしていくでしょう。
これから伸びるブログの特徴
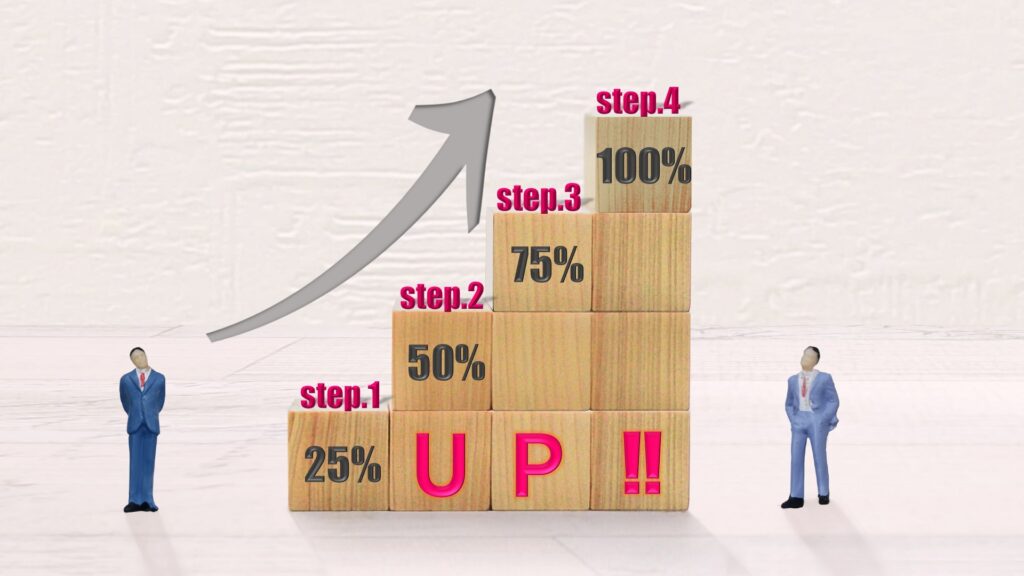
「ブログはオワコンではない」とはいえ、すべてのブログが伸びるわけではありません。これからの時代に成長できるのは、ユーザーの信頼を得られる発信や他にはない価値を提供できるブログです。ここでは、これから伸びるブログに共通する具体的な特徴を解説します。
ニッチなジャンルのブログは伸びやすい
広く浅いテーマを扱う雑記ブログは競合が多いことから、検索上位を取るのが難しくなっています。一方、特定のジャンルに絞ったブログは競争相手が少なく、専門性が評価されやすい傾向にあります。
ここで注目したいのが、特定のジャンルをさらに絞った「ニッチなジャンル」です。例えば、英語学習のジャンルを「ビジネス英語の独学法」とテーマを絞ることで、読者のニーズにピンポイントで応えられるようになります。
ニッチなジャンルは読者層が限定されるぶん強い共感や信頼を得やすく、継続的なアクセスにつながります。
ユーザーの疑問や悩みに答えるブログは支持される
これから伸びるブログに共通するのは、読者が抱える具体的な疑問や悩みにしっかり答えてくれることです。
例えば、「ダイエット 食事制限 きつい」と検索した人は、単なる理論ではなく「無理なく続けられる食事法」を知りたいと考えています。こうしたニーズに沿った記事は読者の信頼を得やすく、リピート訪問やSNSでのシェアにつながります。
反対に、自己満足的なブログや一般論を寄せ集めたブログは支持されにくく、アクセスも安定しません。読者の課題解決を意識することが、ブログを伸ばすための重要なポイントです。
信頼性と専門性の高いブログは評価される
ブログが伸びるかどうかは、どれだけ信頼できる情報を提供できるかにかかっています。金融・医療などの分野を代表に、根拠のない情報や体験談だけの記事は評価されにくく、評価を得るには正確なデータや専門的な知識に基づく発信が必要です。
専門書や公的機関の資料を引用したり、実務経験を基に解説したりすることで、記事の信頼性は格段に高まります。
専門的かつ正確な情報を発信し続けることで「このテーマならこのブログ」と認識されやすくなり、検索エンジンからの評価だけでなく、読者からの支持もアップしますよ。

ブログをオワコンにさせない運営のコツ

どんなに環境が厳しくても、工夫次第でブログは十分に成果を出せます。そのためには、アクセスを集める仕組みを作ったり、読者に信頼される発信を意識したりすることが大切。ここでは、ブログをオワコンにさせない運営のコツを解説します。
キーワード選定とSEO対策
ブログを成長させるには、読者が検索に使う「キーワード」を意識して記事を書くことが大切です。検索数の多い人気キーワードはライバルが多く、結果として上位表示されにくくなります。
そこでおすすめなのが、「英会話」よりも「社会人 英会話 独学」といった複数語の組み合わせた「ロングテールキーワード」です。ロングテールキーワードを使った記事は読者の具体的な悩みに応えやすく、安定したアクセスにつながります。
見出しを整理したり、関連記事同士を内部リンクで結んだりすればSEO対策にもなり、検索エンジンから評価されやすくなりますよ。

SNSやYouTubeを組み合わせて流入を増やす
SNSやYouTubeと組み合わせて情報を発信することで、検索エンジン以外からの流入を見込めます。例えば、記事の一部をX(旧Twitter)やInstagramに投稿してリンクを貼れば、興味を持った人がブログに訪れてくれます。
YouTubeでは記事内容を動画で解説し、概要欄にブログ記事へのリンクを載せるのも効果的です。検索だけに頼らず複数の経路を確保しておくことで、アルゴリズム変動によるアクセス減少のリスクを減らせます。
SNSや動画を活用した複合的な発信は、これからのブログ運営には欠かせない要素です。
特化ブログで専門性を高めて差別化する
幅広いテーマを扱う雑記ブログは、同じような記事が増えやすいことから差別化が難しくなります。そこで有効なのが、テーマを絞った「特化ブログ」です。
特定のジャンルに集中して記事を書き続けることで、読者から「この分野に詳しいブログ」と認識され、信頼性も高まります。検索エンジンからも専門性のあるサイトとして評価されやすく、上位表示も期待できます。
記事同士の関連性が強まるため、内部リンクを活用すれば回遊性がアップし、読者が長く滞在してくれるようになりますよ。
継続的に記事を発信し続ける
ブログの成果は短期間では出ないため、継続して記事を更新し続けることが大切です。記事数が増えることで検索エンジンからの評価が高まり、関連するキーワードでの表示機会も広がります。
定期的に更新されるブログは読者から信頼されやすく、情報に信頼性があればリピーターも増えていきます。さらに、過去の記事を定期的にリライトすれば情報の鮮度を保てるため、検索順位の維持や改善にもつながりますよ。
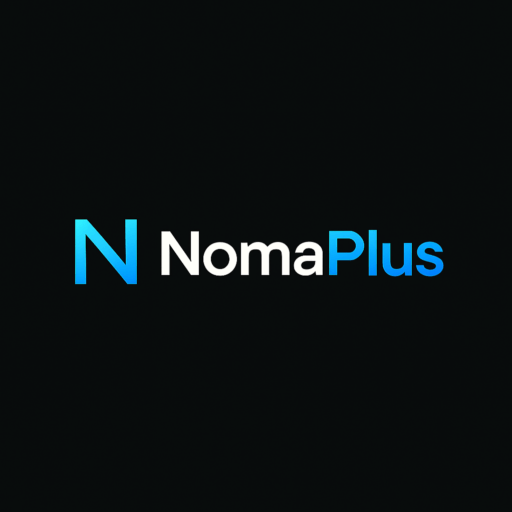 NOMA+運営局
NOMA+運営局何からしたらいいかわからないという方は、以下のサービスを検討してみましょう。サービス利用の方にはSEO対策付きのAIツールを無料でプレゼントしています。
STOPオワコン化!AI時代のブログの書き方


AIツールの進化により、ブログの書き方や運営方法も大きく変わりつつあります。従来の方法だけに頼っていると「オワコン化」してしまう可能性があるので、AIをうまく取り入れて時代の波に乗っていきましょう。
ここでは、AI時代に対応したブログの書き方を解説します。
記事作成やリライトにAIツールを活用する
記事を一から書くには多くの時間と労力を要しますが、AIツールを取り入れれば効率的に進められます。記事の構成案を作成したり、情報を要約・整理したりする作業はAIが得意とする分野です。
また、既存記事をリライトして最新情報を追加する際にも役立ちます。AIを補助的に活用すれば執筆スピードが上がり、記事更新の頻度を保ちやすくなります。
とはいえ、AIはまだまだ補助的な立ち位置です。AIが作成した文章をそのまま使うのではなく、人間の目でしっかりと精査しましょう。


画像・動画生成AIで表現力を高める
ブログは文章が中心ですが、読者の理解を助ける、記事の印象を強めるには画像や動画の活用も欠かせません。最近はAIを使ってオリジナルの画像や図解を生成したり、短い動画を作成したりできるようになっているため、積極的に取り入れていきましょう。
これらを記事に取り入れることで視覚的にわかりやすく、ほかのブログとの差別化にもなります。文章だけでは理解できないような複雑な情報を説明する際には、図解や動画があることで読者も理解しやすくなりますよ。
AIと人間の体験を組み合わせて独自性を出す
AIは情報整理や文章生成に優れていますが、実際の体験や感情に基づいたリアルな情報までは提供できません。そこで重要になるのが、AIが作った土台に自分自身の経験や意見を組み合わせることです。
AIで記事の骨組みを作り、そこに自分が試した商品レビューや失敗談を加えれば、読者にとって説得力のある記事になります。AIと人間の強みを掛け合わせることが、これからのブログ運営で重要になってくるでしょう。
まとめ|ブログはまだオワコンではないが、生き残る工夫は必要!
「ブログはオワコン」といわれる背景には、SEOの難化やSNS・動画の台頭、企業メディアの参入といった要因があります。しかし、インターネット広告市場の拡大や読者からの信頼、テキスト情報への根強い需要を考えれば、ブログは依然として有効な発信手段です。
これから伸びるのは、ニッチなテーマに特化し、読者の疑問や悩みに答える信頼性の高いブログです。さらに、SEOやSNS連携を意識した運営、そしてAIを取り入れた効率化が欠かせません。
大切なのは、工夫しながら継続して発信し続けること。ブログはまだまだ成果を出せる可能性を秘めています。








コメント