副業をしている会社員の悩みの種となりやすいのが「確定申告」です。確定申告書を作成・送付する方法のひとつに「e-Tax」がありますが、どのような手順で進めるのかわからない方もいるのではないでしょうか。
この記事では、e-Taxを使った確定申告のやり方、確定申告が必要になる条件を解説しています。確定申告をスムーズに進める方法も紹介していますので、ぜひ参考にしてください。
会社員の副業をe-Taxで確定申告する方法

副業で得た収入を税務署に申告するなら、自宅で手続きができる「e-Tax」が便利です。
e-Taxは国税庁が運営する電子申告・納税システムで、副業をしている会社員のほか事業者、年金受給者なども利用できます。ここでは、その流れと必要書類、送信・納付の手順を解説します。
e-Taxを使った確定申告には2つの方法がある
e-Taxでの確定申告には、本業と副業の所得が記載された「確定申告書」が欠かせません。電子申告は書類をパソコンで作る必要があり、その際の選択肢が「確定申告書等作成コーナー」と「会計ソフト・アプリ」です。
確定申告書等作成コーナーは、国税庁が提供する無料の確定申告書作成サービスで、パソコンのほかスマホ、タブレットにも対応しています。
会計ソフトやアプリは「弥生」「マネーフォワード」など、民間企業が提供するソフトウェアです。日々の収入や経費を自動で取り込み、帳簿を作成してくれます。
利便性を求める場合は有料となりますが、電子帳簿保存法に対応していたり、インボイス制度に対応していたりするため効率的です。どちらを選ぶかは、副業の規模や経理の得意不得意で判断するとよいでしょう。
e-Taxで副業の確定申告をする際に必要な書類
e-Taxで副業の確定申告を行う際には、収入や控除に応じた書類を用意しましょう。どのような副業をしていたとしても必要になるのが、本業の勤務先から交付される「源泉徴収票」です。
その上で、給与所得や雑所得、事業所得など所得ごとに必要な書類を用意します。
- 給与所得:アルバイト先の源泉徴収票
- 雑所得・事業所得:支払調書または報酬明細書、帳簿
- 不動産所得:帳簿
雑所得・事業所得・不動産所得の場合は、青色申告決算書や収支内訳書を作成する関係で1年間の収支を記録した帳簿が必要です。売り上げや経費の帳簿記入は「取引が行われたとき」が基本なので、確定申告までに終わらせておきましょう。
住宅ローン控除や医療費控除、ふるさと納税といった各種控除を受ける場合は、それぞれの証明書や受領書も用意しておきましょう。

e-Taxにログインして確定申告書を作成する
e-Taxには「WEB版」と「インストール版」の2つがあります。インストール版はWindowsに限られるため、WEB版での作成方法を紹介します。
確定申告書には「第一表」と「第二表」の2つがあり、副業の確定申告でも両方の作成・提出が必要です。両方とも確定申告書等作成コーナーで作成できますよ。
e-Taxにアクセスし、マイナンバーカード、または利用者識別番号&パスワードでログインします。「確定申告を行う」をクリックすると確定申告書等作成コーナーに移動するので、「作成開始」をクリックして書類を作成しましょう。
まずは「第一表」です。副業の確定申告では、本業の収入・所得と副業で得た収入・所得の両方を記載しなくてはなりません。ここで注意したいのは、所得の種類によって使用する欄が異なること。種類ごとの収入・所得を入力欄は以下の通りです。
| 副業の所得区分 | 収入を書く欄 | 所得を書く欄 |
| 給与所得 | 収入金額等(オ) | 所得金額等(6) |
| 雑所得 | 収入金額等→雑→業務(キ) | 所得金額等→事業→業務(8)、(7)から(9)までの計 |
| 事業所得 | 収入金額等→事業→営業等(ア) | 所得金額等→事業→営業等(1) |
| 不動産所得 | 収入金額等(ウ) | 所得金額等(3) |
所得とは「収入から経費、または給与所得控除を引いた金額」です。給与所得は原則として経費が認められていないため、所得を書く欄には「給与所得控除」を引いた金額を記載します。
源泉徴収票に書かれている社会保険料を「社会保険料控除」の欄に入力します。給与所得の場合は、合算した金額を入力しましょう。医療費控除や生命保険料控除などがあれば入力し、最後に所得税を計算して「税金の計算」の欄に入力します。
すべての入力が終わると自動で税額が計算され、還付や納付の金額が表示されたら「第一表」は完成です。
「第二表」は、第一表の内容を詳細に書く書類です。「所得の内訳」に所得を得た勤務先や取引先、それぞれの金額を入力します。同じように、社会保険料や控除の詳細も記載しましょう。
本業の住民税は給与から天引きされますが、副業の収入に対する住民税は給与所得であっても天引きされません。副業分のみ自分で納付するという場合は、住民税の欄にある「自分で納付」に◯を付けましょう。「特別徴収」に◯を付けると、本業の給与から天引きされます。
すべての入力が終わったら内容を確認して保存し、e-Tax送信に進めば完了です。


e-Taxでの確定申告が必要になる副業の条件

副業をしている会社員全員が、確定申告をしなくてならないわけではありません。
所得の種類や金額によっては申告義務が発生しないケースもあるため、どのような場合に確定申告が必要になるのかの「条件」を理解しておきましょう。
20万円ルールの基本と注意点
副業に関する「20万円ルール」を知っていますか。20万円ルールの「20万円」は、確定申告が必要になる年間所得のラインとなり、副業の年間所得が20万円以上の場合は確定申告が必要、20万円以上の場合は確定申告が不要です。
ただし、医療費控除や住宅ローン控除、ふるさと納税の控除を受けたい場合は、副業の年間所得が20万円以上であっても確定申告をしなくてはなりません。
20万円ルールはあくまでも副業の年間所得だけに適用されるので、控除の申請をする場合は例外だと覚えておきましょう。
所得区分の種類と違い
副業で得た収入はその内容によって所得区分が異なり、書類の作成方法も変わります。確定申告が必要になる条件に違いはありませんが、確定申告のやり方は所得によって変わるため注意しましょう。
アルバイトなど給与として支払われるものは「給与所得」となり、勤務先から交付される源泉徴収票を基に記入します。
データ入力やWebライティングなど単発で受ける委託業務、ポイ活などは「雑所得」、フリーランスとして継続的に収入を得ている場合は「事業所得」、不動産を貸している場合は「不動産所得」に分類されます。
この3つの所得に共通しているのは、経費が認められていること。所得を算出するには収入と経費両方の金額が必要になるため、それを記録する帳簿、お金を支払ったことを証明する領収書(レシート)の用意も必須です。

e-Taxの確定申告で使う青色申告と白色申告の違い

確定申告には「青色申告」と「白色申告」の2つの方法があり、それぞれ特徴があります。また、収入によって向き不向きもあるため、青色申告と白色申告の違いを理解しておくことが大切です。
ここでは、青色申告と白色申告の違い、それぞれに向いている人を解説します。
青色申告の特徴と向いている人
青色申告は、副業を事業として行う人に向いている申告方法です。最大の特徴は「青色申告特別控除」で、要件を満たすと最大65万円の控除を受けられます。
具体的な条件は、複式簿記で帳簿をつける、電子帳簿保存法に対応した形で記録する、e-Taxを使って確定申告をすることです。簡易的な帳簿のみで申告する場合でも、最大10万円の控除を受けられますよ。
青色申告は「事業所得」「不動産所得」「山林所得」のいずれかで所得を得ている場合にのみ利用できるので、給与所得や雑所得の場合は必然的に白色申告となります。
確定申告においては、確定申告書第一表と第二表に加え、青色申告決算書や損益計算書、貸借対照表なども作らなくてはなりません。
また、事前に「青色申告承認申請書」を税務署に提出する必要があるため、メリットは多いものの条件が多く、利用者が絞られる方法といえるでしょう。

白色申告の特徴と向いている人
白色申告は、収入がそこまで多くない人や、簿記が苦手な人に向いている申告方法です。青色申告のような特別控除はないものの、控除がないため単式簿記を選んでも損をしません。
デメリットは、青色申告に比べると節税効果は小さいこと。副業が軌道に乗って収入が増えると支払う税金が多くなるため、副業をしているメリットを感じにくくなるかもしれません。
しかし、確定申告では確定申告書第一表と第二表と収支内訳書(給与所得を除く)を提出するだけで済むため、青色申告ほど書類作成に時間がかかりませんよ。
e-Tax以外の確定申告書提出方法
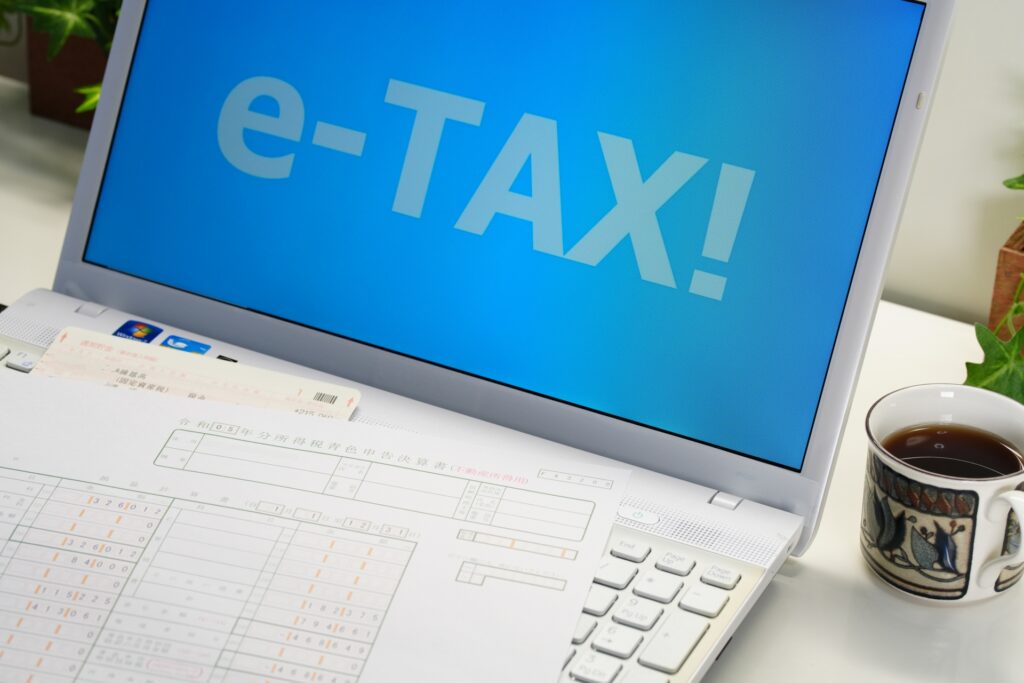
e-Taxは便利な申告方法ですが、必ず利用しなければならないわけではありません。自分に合ったやり方を選べるよう、e-Tax以外にも確定申告の方法が用意されています。
まずは、紙で作成した確定申告書を郵送する方法です。A4サイズの紙が入る「角形2号」に確定申告書やそのほかの書類を入れ、管轄の税務署宛に「郵便物」または「信書便物」で送付しましょう。
確定申告は宅配便やメール便では送れず、提出日が消印の日付となります。消印が最終期限の3月15日を過ぎると期限後申告になる可能性があるため、提出するタイミングに注意しましょう。
次に、税務署の窓口に確定申告書を持ち込む方法です。職員に確認してもらいたい場合は税務署の開庁時間内にいく必要がありますが、時間外収受箱があるため閉庁後でも提出できます。
地域によっては、確定申告シーズンのみ土日も開庁している場合があるため、事前に調べておくとよいでしょう。
副業の確定申告をスムーズに進める方法
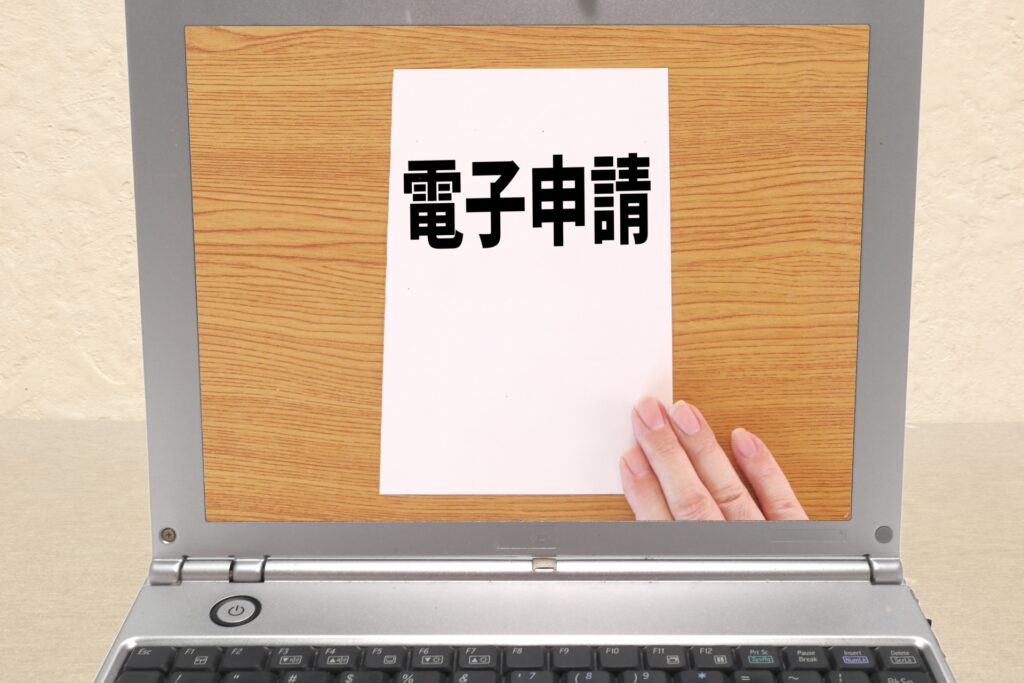
副業の確定申告は書類の準備、入力作業などやることが多いため、直前になって慌ててしまう人も少なくありません。
スムーズに進めるためには、効率的なツールを活用することと、日々の記録をきちんと残すことが重要です。ここでは、会計ソフトの活用と帳簿をこまめにつける工夫について解説します。
会計ソフトを活用する
確定申告書は収入から経費や控除類を差し引くので、手書きにすると計算ミスが起こる可能性もあります。会計ソフトは銀行口座やクレジットカードと連携して取引を自動で取り込み、仕訳を自動化できるため、手間やミスを減らせます。
近年はAIを搭載したソフトも増えており、取引内容から勘定科目を自動で提案してくれるなど、さらに便利になりました。
青色申告で必要な複式簿記の帳簿も自動作成され、e-Taxと連携できるサービスなら申告書の送信まで完結可能です。時間や労力を削減し、ミスを防ぎたい人にとって、AI機能を備えた会計ソフトは非常に有効な選択肢といえるでしょう。
\おすすめの会計ソフト/
日々の帳簿をこまめにつける
確定申告をスムーズに進めるには、確定申告書を作成する前から準備を始めることが大切です。
雑所得や事業所得、不動産所得の場合、帳簿がなければ収支を計算できません。1年分をまとめて処理しようとすると、領収書の紛失や記憶の曖昧さから誤記入が増え、修正に時間がかかります。
電子帳簿保存法に対応する場合、紙の領収書は2か月と7日以内に電子化しなくてはならないため、確定申告シーズンに帳簿をつけると特別控除の条件から外れてしまいます。
副業が本業と並行して忙しくなりがちな会社員こそ、日々の記録を習慣化しておくことが、確定申告を乗り切るためのベストな方法といえるでしょう。
まとめ|会社員の副業はe-Taxで確定申告するのが便利
会社員の副業も、年間所得が20万円以上になったら確定申告をしなくてはなりません。その手続きを効率的に行えるのが、国税庁が提供するオンラインサービス「e-Tax」です。
e-Taxを使えば、申告書の作成から送信までが自宅で完結します。しかし、確定申告書を直接入力すると時間がかかる、ミスをしやすくなるなどの問題が出てくるため、効率良く進めるために会計ソフトを導入してみましょう。
会計ソフトは確定申告書だけでなく、日々の帳簿管理も効率化してくれます。AI機能を搭載している、e-Taxと連携しているなど特徴もそれぞれなので、自分に合ったものを選んでくださいね。












コメント