フリーランスと会社員では、同じ年収でも手取り額に大きな差が出ることを知っていますか。その理由は、税金や社会保険料の仕組みの違いにあります。
この記事では、両者の手取りの違いを年収別に比較し、フリーランスが手取りを増やす方法や独立前に知っておきたい注意点を解説します。働き方を選ぶうえでの判断材料として、ぜひご活用ください。
フリーランスと会社員の手取りを比較する際のチェックポイント

フリーランスと会社員の手取りを正しく比較するには、比較の「前提」をそろえることが大切です。手取りの定義や税金・保険料の仕組み、有給休暇やボーナスなど、比較する上で見落としやすい要素を紹介します。
そもそも「手取り」とは?
手取りとは、額面の収入から税金や社会保険料などを差し引いた後に、実際に受け取れるお金のことです。
会社員は給与から所得税・住民税・健康保険料・厚生年金・雇用保険などが天引きされ、その残りが口座に振り込まれます。そのため、月の手取りは「口座に振り込まれた金額」です。
一方のフリーランスは、所得税・住民税・健康保険料などを自分で納めるため、原則として報酬の全額が口座に振り込まれます。そのため、フリーランスの手取りは「税金などをすべて支払い終わった後の金額」となります。
税金・年金・保険料の種類と支払い方法の違い
会社員とフリーランスでは、支払う税金や保険料の内容と方法に違いがあります。会社員は所得税と住民税、社会保険料(健康保険・介護保険・厚生年金・雇用保険・労災保険)が給与から天引きされるため、自分で支払うことはありません。
一方フリーランスは、所得税や住民税、国民健康保険料、国民年金などを自分で納めます。納付方法も口座振替やコンビニ払い、前納・後納の選択などがあり、支払いも管理もすべて自己責任です。
フリーランスには有給とボーナスがない
収入に関する会社員とフリーランスの大きな違いに、有給休暇とボーナス(賞与)があります。
会社員は、労働基準法により有給休暇取得の権利が与えられています。休暇を取得しても給与が減らない仕組みがあるため、収入の安定性につながります。また、多くの会社では就業規則や労使契約に基づいてボーナスが支給されることもあります。
一方のフリーランスには有給休暇やボーナスといった制度がなく、休めば収入は途絶え、臨時収入もありません。年収が同じ金額であっても、会社員には「実際に働いて得る収入とは異なる性質の収入」があり、フリーランスにはそれがないという差が生じます。
フリーランスと会社員の手取りを年収別に比較

フリーランスと会社員の手取りの違いは、具体的な年収に当てはめると理解しやすくなります。ここでは、年収300万円・500万円・800万円・1,000万円それぞれの手取りの違いを、シミュレーションしながら解説します。
なお、住民税と国民健康保険料は東京都23区を基準としています。
年収300万円の場合
年収300万円では、会社員とフリーランスの手取り差はそこまでありません。会社員は給与所得控除や会社負担の社会保険によって手取りを確保しやすく、生活費を賄える安定感があります。
一方フリーランスは国民健康保険や国民年金を全額負担するため、同じ年収でも手取りはやや減少します。しかし、経費をしっかり計上できれば課税所得を抑えられるため、実際の差はケースによって変動します。
| 会社員 | フリーランス(青色申告) | |
|---|---|---|
| 年収(額面) | 300万円 | 300万円 |
| 健康保険料・年金など | 約45万円 | 約60万円 |
| 所得税 | 約8万円 | 約7万円(青色65万円控除適用後) |
| 住民税 | 約16万円 | 約16万円 |
| 手取り額 | 約231万円 | 約217万円 |
年収500万円の場合
年収500万円では、累進課税による影響が見え始めます。会社員は給与所得控除があるため課税所得を抑えられますが、それでも所得税・住民税の負担が重くなります。
フリーランスは保険料の全額負担が年収300万円以上に効いてくるため、青色申告控除を活用しても手取りは伸びません。年収300万円台と比べると、差はさらに拡大します。
| 会社員 | フリーランス(青色申告) | |
|---|---|---|
| 年収(額面) | 500万円 | 500万円 |
| 健康保険料・年金など | 約75万円 | 約110万円 |
| 所得税 | 約25万円 | 約22万円(青色65万円控除適用後) |
| 住民税 | 約30万円 | 約30万円 |
| 手取り額 | 約370万円 | 約338万円 |
年収800万円の場合
年収800万円になると、高所得層として税負担が大きくのしかかります。会社員は給与所得控除で一定の軽減を受けられるものの、住民税・所得税ともに高額です。
フリーランスは国民健康保険の負担がより一層重くなるため、同じ収入でも自由に使えるお金はさらに減少します。
| 会社員 | フリーランス(青色申告) | |
|---|---|---|
| 年収(額面) | 800万円 | 800万円 |
| 健康保険料・年金など | 約120万円 | 約170万円 |
| 所得税 | 約80万円 | 約75万円(青色65万円控除適用後) |
| 住民税 | 約55万円 | 約55万円 |
| 手取り額 | 約545万円 | 約500万円 |
年収1,000万円の場合
年収1,000万円では、手取り率がおおよそ6割前後まで下がります。会社員は高額所得者としての税負担が大きいものの、社会保険料は会社と折半されるため一定のバランスが保たれます。
一方フリーランスは国保・国民年金や税金がさらに増えるため、負担は増すばかりです。収入が大きくても、実際に手元に残る金額は想像以上に少ないことが分かります。年収900万円を常に超えるようであれば、法人化を視野に入れてもよいでしょう。
| 会社員 | フリーランス(青色申告) | |
|---|---|---|
| 年収(額面) | 1,000万円 | 1,000万円 |
| 健康保険料・年金など | 約150万円 | 約200万円 |
| 所得税 | 約140万円 | 約75万円(青色65万円控除適用後) |
| 住民税 | 約70万円 | 約70万円 |
| 手取り額 | 約640万円 | 約600万円 |
フリーランスが会社員より手取りを増やす4つの方法

フリーランスは報酬の全額を受け取れる一方で、税金や保険料を自分で負担しなければならないため、会社員に比べて手取りは少なくなる傾向にあります。しかし、正しい方法で工夫をすれば、手元に残るお金を増やすことが可能です。
ここでは、フリーランスの手取りを増やす4つの方法を紹介します。
経費を正しく計上する
フリーランスは収入から必要経費を差し引いた「課税所得」に対して税金がかかります。そのため、経費を正しく計上することが手取りを増やす大きなポイントです。
仕事に必要なパソコンやソフト代、通信費、書籍代などは経費として認められるため、適切に申告すれば課税所得を減らせます。ただし、減価償却が必要な物は原則として耐用年数の期間で償却していくため、経費のすべてが一度に計上できるわけではない点に注意しましょう。
なお、プライベートで使ったお金は経費として計上できません。うっかりだとしても、税務調査で否認される可能性があるため、仕事用と私用をしっかり分けて管理しましょう。

青色申告を利用する
フリーランスの確定申告には「白色申告」と「青色申告」の2種類があります。帳簿づけの要件が少なく手続きも簡単ですが、適用されるのは基礎控除48万円のみです。
これに対して青色申告は、複式簿記による記帳や帳簿保存が必要になるものの、基礎控除48万円に加えて最大65万円の青色申告特別控除を受けられます。
会社員の場合は給与所得控除(最低55万円〜収入に応じて増加)が自動的に適用され、さらに基礎控除48万円も差し引かれます。
白色申告のフリーランスは控除額で会社員に劣りますが、青色申告を選べば会社員に近い水準まで課税所得を圧縮できるため、手取りを増やすのであれば青色申告を利用するのがおすすめです。

単価アップと案件獲得の工夫をする
フリーランスの手取りを増やすには、税金対策に加えて「収入そのものを増やす工夫」も大切。まず意識したいのは案件単価の引き上げです。スキルを磨き、専門性の高い分野で実績を積めば、同じ労働時間でもより高い報酬を得られます。
また、複数のクライアントと契約することで、安定性を確保しつつ収入アップのチャンスを広げられます。いつでも契約できるようにポートフォリオを整え、エージェントやクラウドソーシングを活用して案件獲得のアンテナを張っておきましょう。
効率的に単価を上げ、安定した案件を獲得することが、フリーランスの手取りを底上げする確実な方法となります。

資産形成や節税制度の活用
フリーランスには退職金制度や企業年金がないため、自分で将来に備える必要があります。その際にまず検討したいのが「小規模企業共済」です。
これはフリーランスや中小企業の経営者向けの退職金制度で、掛金は全額所得控除の対象になります。積み立てながら節税ができるため、老後資金の準備と手取りの確保を同時に進められますよ。
加えて、iDeCo(個人型確定拠出年金)は掛金が全額所得控除となり、将来の年金を積み立てつつ節税効果も得られます。さらに、NISAを利用すれば運用益が非課税となり、効率的な資産形成が可能です。
会社員からフリーランスに転身するときの準備と注意点

会社員からフリーランスに転身すると、収入の仕組みや社会保障、生活の安定性が大きく変わります。ここでは、会社員からフリーランスへ転身する際に知っておきたい「準備と注意点」を解説します。
無収入期間に備える
フリーランスとして独立した直後は、案件がすぐに見つからなかったり、入金までに時間がかかったりして、収入が一時的に途絶える場合があります。そのようになっても生活できるように、半年〜1年分の生活費を貯めておきましょう。
フリーランスは有給休暇や傷病手当がないため、病気やケガで働けなくなると同じように無収入となります。「生活費を切り詰めれば何とかなる」のは、最初の数回だけです。生活費を切り詰めるだけでは不安定さを解消できないため、無収入を耐えられる最低限の資金を用意しておきましょう。
国民健康保険・国民年金の加入手続きをする
会社員を辞めると同時に、社会保険から脱退することになります。そのためフリーランスとして活動を始める際は、国民健康保険と国民年金への加入手続きが必須です。それぞれの手続きは、住民票のある市区町村役所で退職日の翌日から14日以内に行います。
健康保険については、退職前に加入していた健康保険を任意継続するか、国民健康保険に加入するかを選べますが、年金には任意継続制度がないため国民年金となります。
開業届やインボイスの登録申請をする
フリーランスとして事業を始める際には、まず税務署に「開業届」を提出します。これにより、個人事業主として正式に事業を開始したことが公的に認められます。
開業届と一緒に「青色申告承認申請書」を提出することで、最大65万円の青色申告特別控除を利用できるようになるため、初年度からある程度の収入が見込めそうな場合は青色申告の手続きも行いましょう。
2023年に導入されたインボイス制度により、取引先に適格請求書の発行を求める企業が増えています。適格請求書を発行するにはインボイス発行事業者への登録が必要になり、登録することで自動的に課税事業者となります。インボイス発行事業者への登録は現在「任意」のため、どうするかをじっくりと考えましょう。
契約書・請求書など業務体制を整える
フリーランスは会社のような総務部門がないため、契約や請求の体制を自分で整える必要があります。
契約書は業務範囲や報酬、支払い条件、著作権や秘密保持などを明記しておくことで、後々のトラブルを防げます。請求書については、インボイス制度に対応した形式を準備しておくと安心です。登録番号や税率区分、振込先など、必要な項目を漏れなく記載しましょう。
テンプレートを作ったり、会計ソフトと連携したりすれば、発行から入金まで効率的に管理できます。
クレジットカードやローンの申請に注意!
フリーランスになると社会的信用度が下がるため、クレジットカードやローンの審査は会社員時代より厳しくなります。クレジットカードについては、独立直後だと新規発行や限度額の増額がスムーズにできない場合もあるため、必要であれば会社員のうちに準備しておきましょう。
ローンは、クレジットカード以上に審査が厳しくなります。会社員時代に組めば審査は通りやすくなりますが、収入が不安定になる可能性を考えると収入が安定するまでローンを組まない、借入の必要がないタイミングで独立するのが理想です。
\経費に使えるおすすめクレカ/
リスクを減らすなら副業から始めよう
会社員からフリーランスに転身する際は、いきなり独立するよりも、副業として始めて実績を積むほうが安全です。副業であれば会社員としての安定収入を維持しながら、仕事の獲得方法や案件の進め方、確定申告の流れを実践的に学べます。
収入が増えて案件が安定してきた段階で独立すれば、無収入期間を避けられるだけでなく、独立初年度から安定した収入を確保できる可能性が高まります。また、副業を通じてスキルや人脈を広げておくことは、フリーランスとして長く活動していくための大きな武器になりますよ。
職種ごとに見るフリーランスの手取りの傾向
フリーランスの手取りは、職種によって大きく変わります。単価が高い分野もあれば、競争の激しさから収入が伸びにくい分野もあるため、将来設計のひとつとして傾向をつかんでおきましょう。ここでは、フリーランスに多い職種ごとに、手取りの特徴を紹介します。
エンジニア
エンジニアは単価・需要ともに高い職種です。システム開発やWebサービス、アプリ制作など、幅広い分野でプロジェクトがあり、スキルに応じて高単価の案件を獲得できます。
会社員のエンジニアが年収500万円前後であるのに対し、フリーランスでは同水準かそれ以上の報酬を得られるケースも多く、効率良く受注できれば会社員の手取りを上回ることも。
フリーランスとして働くには自ら継続的に学習し、最新の技術を身につける努力が欠かせません。高単価案件を受けたとしても契約が途切れれば収入が不安定になるため、安定して稼ぐには案件の継続確保が大きな課題となります。
\▼▼▼おすすめのプログラミング情報▼▼▼/
デザイナー・クリエイター
デザイナーやクリエイターは、Webデザイン・グラフィック制作・動画編集など幅広い分野で活躍できます。需要は安定していますが、案件単価はエンジニアほど高くありません。
駆け出しのころは数万円程度の小規模案件が中心になり、会社員時代と同じ水準の手取りを確保するには数をこなす必要があります。スキルを高めてディレクションやブランディングなど上流工程に関わったり、動画やUI・UXといった需要の高い分野に特化したりすることで、単価アップを実現できますよ。
競争が激しい分野ではありますが、継続案件を得られるクライアントと契約できれば、安定した手取りを目指せます。
\▼▼▼おすすめのデザインスクール▼▼▼/
ライター
ライターは参入のハードルが低く、未経験から始めやすい職種です。ブログ記事や取材記事、SEO記事の執筆など幅広い案件があるものの、ある程度経験を積むまでは1文字0.5円〜1円程度の案件が中心になり、多くの記事を書いても生活できるほど稼げないこともあります。
単価アップのポイントは、専門分野に特化した高品質な記事を書けるようになることです。また、ライターだけでなく校正や編集、ディレクターなどの仕事もできるようになると付加価値をつけられますよ。
\NOMA+読者限定!/
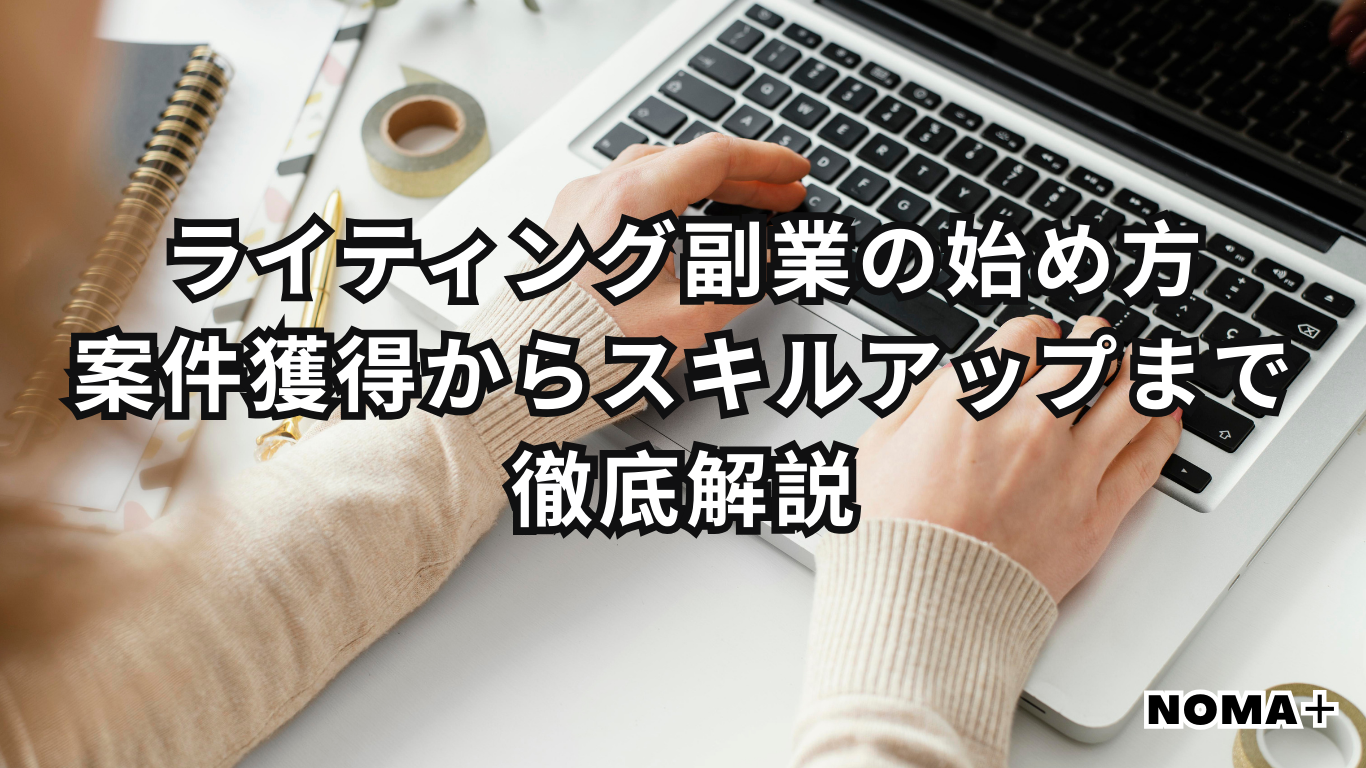

コンサルタント
コンサルタントはフリーランスの中でも案件単価が非常に高い職種です。経営戦略・人事制度・マーケティング・IT導入支援など専門性の高い領域で求められることが多く、1案件あたり数十万円から100万円以上になることも珍しくありません。
しかし、報酬水準が高いぶん豊富な実務経験や実績・専門知識が求められ、実績がない状態で独立すると案件獲得は難しく、信頼を得るまでは不安定な時期が続くことも。
企業の経営層や意思決定層と直接やり取りすることが多いため、高度なコミュニケーション能力や責任感も欠かせません。実力次第で大きな収入を得られる反面、参入のハードルは高い職種といえます。
フリーランスと会社員の手取りの比較に関するよくある質問

フリーランスと会社員の手取りを比較する際、多くの人が同じような疑問を持ちます。ここでは、会社員並みの手取りを得るにはいくら稼げばいいのか、有給休暇や雇用保険はあるのかなどのよくある質問とその回答をわかりやすく解説します。
会社員並みの手取りに必要な売り上げは?
フリーランスの手取りは、会社員と同じ年収でも少なくなりがちです。会社員は健康保険や厚生年金などの社会保険料を会社と折半していますが、フリーランスはこれらを全額自己負担するためです。
会社員と同等の手取りを得るには、1.3倍〜1.5倍程度の売り上げが必要だといわれています。例えば、400万円の手取りであれば売り上げは500万〜600万円です。
フリーランスに有給休暇や雇用保険はある?
いいえ、フリーランスには有給休暇や雇用保険はありません。休めばそのぶんだけ収入が減り、仕事が途切れても失業給付は受けられません。保障を補うには、生活防衛資金の確保や民間保険の活用が必要です。
源泉徴収がある報酬とない報酬の違い
フリーランスの報酬には、源泉徴収が行われるものと行われないものがあり、原稿料やデザイン料、講演料などが源泉徴収の対象となります。
源泉徴収される仕事の場合は報酬から所得税(10.21%)が差し引かれ、確定申告後に払い過ぎたぶんが還付されます。源泉徴収されない仕事に関しては、確定申告で所得税額を決定し、その金額を納付します。
インボイス制度で手取りは減る?
インボイス(適格請求書)は複数税率に対応した仕入税額控除方式を指し、インボイスを使って消費税を正しく納めるための制度をインボイス制度といいます。
フリーランスの場合、インボイス発行事業者に登録するかしないかは任意で決められますが、登録することで課税事業者となり、売り上げに応じて消費税を納めなくてはならなくなります。
消費税分のお金が出ていくことになるため、インボイス制度に登録すれば手取りは減ります。

まとめ|フリーランスの手取りは税金・保険料の仕組みにより会社員よりも少なくなる
フリーランスと会社員は税金や保険料などの仕組みが異なるため、同じ年収であれば基本的に会社員のほうが手取りは多くなります。
しかし、フリーランスは自分で仕事を増やしたり、高い単価の案件に挑戦できたりするため、月の収入を自分で調整できます。また、青色申告を利用することで控除額が増え、手取りを増やせますよ。
しかし、仕事がないときや、病気・ケガで休んだときの保障はないため、ある程度の貯金は必要です。すぐに独立ではなく、副業から始める手もあります。リスクや現状を踏まえて、自分なりの進め方を見つけてください。

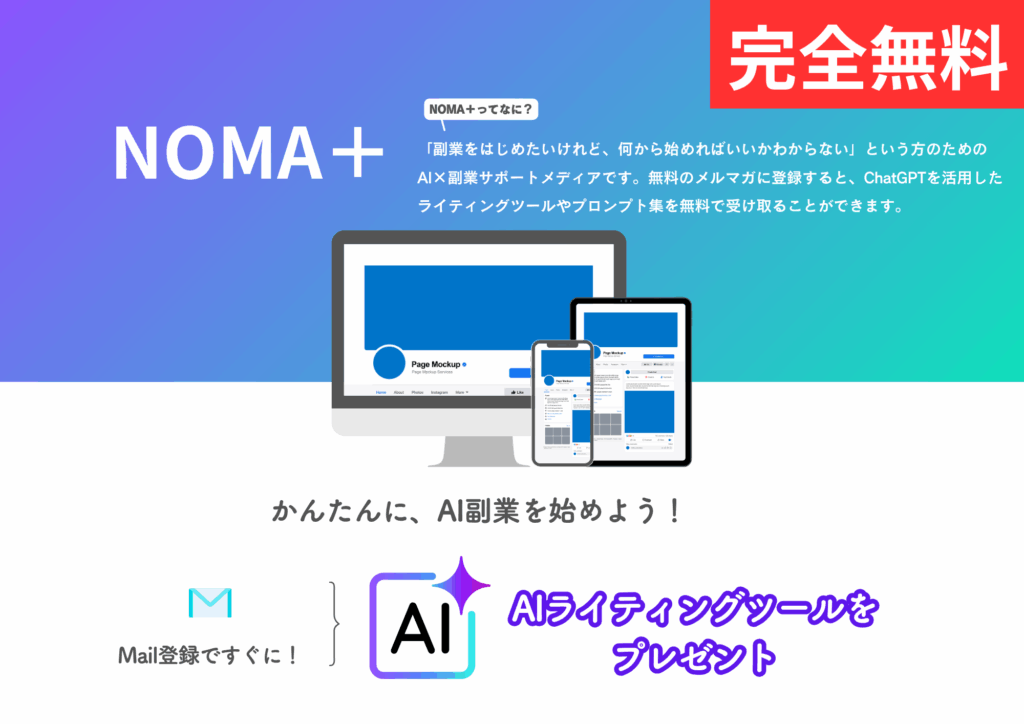






コメント