会社員が副業をすると、副業先から「源泉徴収票」が届く場合があります。なんのために届いているのか、受け取ったものをどうすればいいのかと、悩む人もいるでしょう。
この記事では、副業先から源泉徴収票が届く理由、源泉徴収票を使った確定申告の流れを解説します。確定申告をスムーズに進める方法も紹介しますので、ぜひ参考にしてください。
副業をしたら源泉徴収票が届く理由
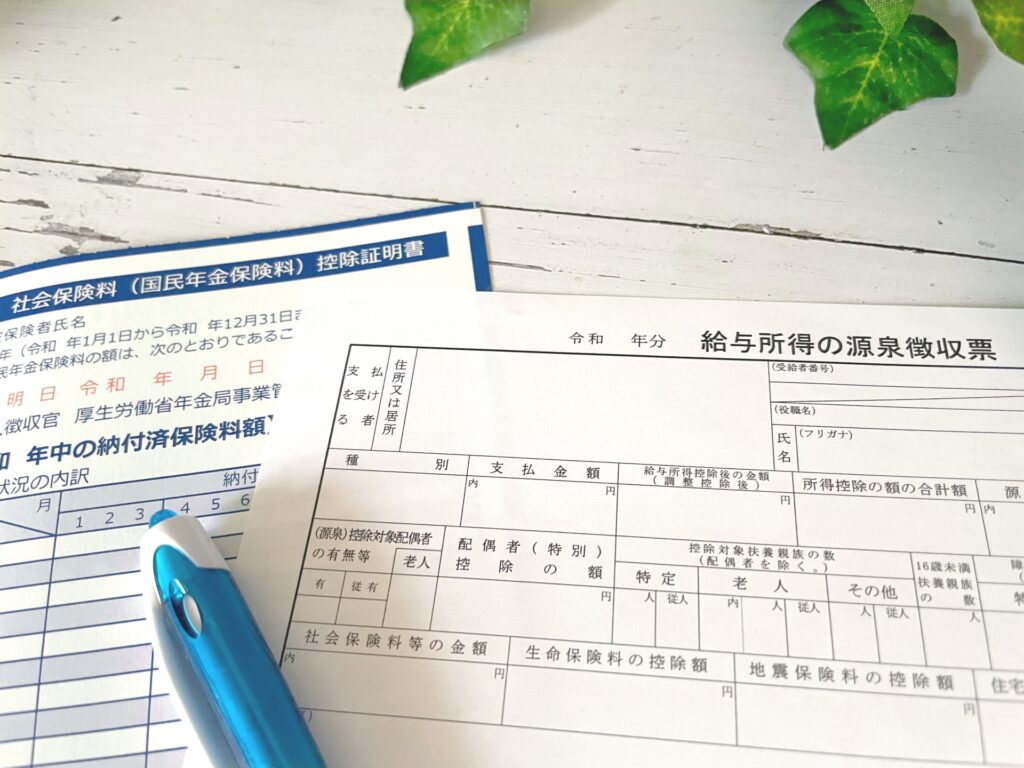
会社員が副業を始めると、本業とは別に副業先から「源泉徴収票」が届きます。本業で年末調整をしているにもかかわらず、なぜ源泉徴収票が送られてくるのでしょうか。
ここでは、副業先から源泉徴収票を渡される理由を解説します。
確定申告が必要だから
副業先から源泉徴収票が送られてくるのは、本業以外で得た収入についても確定申告が必要になるためです。
会社員をはじめとした給与所得者は、給与から所得税が源泉徴収され、年末調整を行うことで差額分を精算します。しかし、年末調整は「1つの場所でしかできない」ため、副業分は源泉徴収されたままの状態となります。
本業と副業の源泉徴収を合算し、確定申告をすることで納めるべき正しい所得税が計算できるのです。
源泉徴収票は「年間の給与がいくらで、いくら税金を引いたか」を記した書類なので、届いたからといって必ず確定申告が必要になるわけではありません。
なお、源泉徴収票は「対象となる年の翌年1月末まで」に渡されます。
源泉徴収と年末調整の違い
源泉徴収とは、給与支給時にあらかじめ所得税を差し引く仕組みです。毎月の給与から一定額が天引きされますが、「給与所得の源泉徴収税額表(月額表)」を用いて出した概算額なので、実際に納める所得税額ではありません。
一方の年末調整は、その年の総収入と控除額を基に正しい税額を算出し、源泉徴収との過不足を精算する手続きです。会社員は勤務先が年末調整を行うため、確定申告をしなくても税金の精算が完了します。
源泉徴収は毎月の給料から引かれるもの、年末調整はその年の年末に行われる税金の精算と理解しましょう。

副業をしたら必ず源泉徴収されるの?
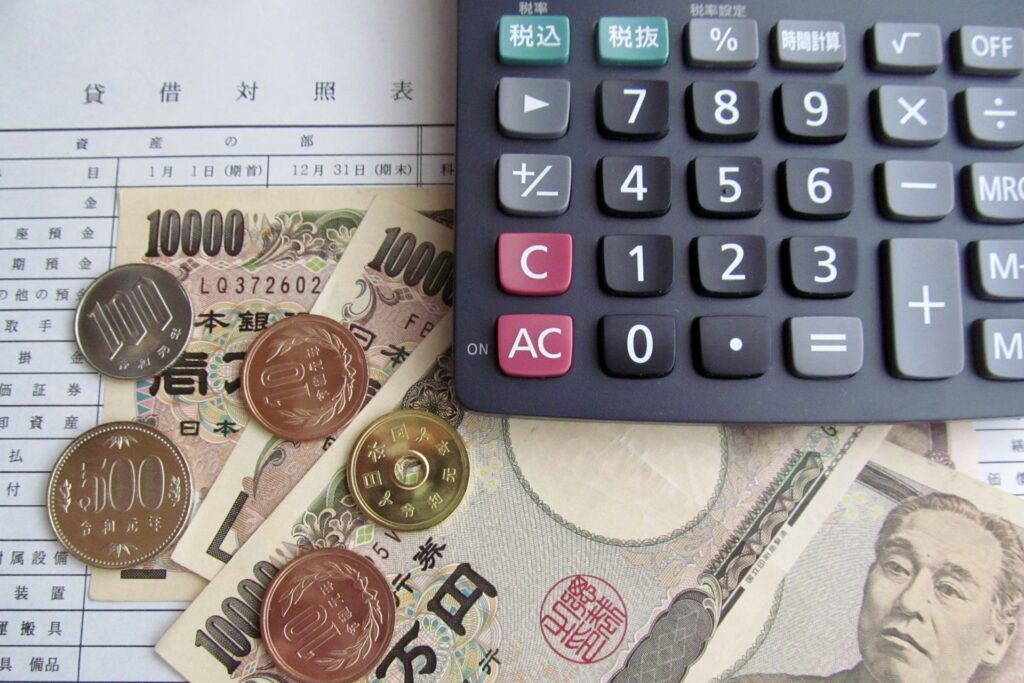
源泉徴収されるのは多くの場合給与所得者ですが、給与所得以外の所得でも行われる場合があります。副業をやっている人の中に、源泉徴収票をもらっている人ともらっていない人がいるのはこのためです。
ここでは、副業の所得区分ごとに源泉徴収の有無を整理します。
給与所得の場合
副業がアルバイトやパートといった「給与所得」に当たる場合、原則として副業先でも源泉徴収が行われます。これは本業と同じで、毎月の給与から所得税が天引きされるためです。
本業分の所得税は年末調整で精算されますが、副業先では年末調整が行えないため、副業分の所得税は概算額が引かれたままの状態になっています。
この概算額は、本来の所得税より多い場合と少ない場合があり、払いすぎている場合は放置すると損することになります。反対に、少ない場合は無申告課税などのペナルティが課されることも。
正しい税額を出すために、本業と副業両方の源泉徴収票を使って確定申告を行いましょう。
雑所得・事業所得の場合
雑所得や事業所得の場合は、副業の内容によって源泉徴収される・されないが変わります。所得区分だけで分けられない部分もあるため、仕事内容で確認してくださいね。
源泉徴収の対象となる主な仕事は以下のとおりです。
- 原稿料、講演料
- 特定の資格を持つ人(弁護士や税理士)への報酬または料金
- モデル、プロスポーツ選手、外交員への報酬または料金
- コンパニオン、ホステスへの報酬または料金
このほか、Webライターも場合によっては源泉徴収されます。
これらの所得と給与所得の大きな違いは、源泉徴収の有無に関係なく確定申告が必要になること。
源泉徴収されている場合は確定申告に源泉徴収票が必要になるので、送られてくる源泉徴収票を大切に保管しておきましょう。
源泉徴収がないケース
源泉徴収は、原則として給与所得、国が定めた源泉徴収対象の報酬に対して行われるため、これに該当しない副業では源泉徴収が行われません。
たとえば、フリーランスとして受ける委託業務の報酬や不動産収入、ネットビジネスによる収益などは、支払い時に税金が差し引かれずに全額振り込まれるのが一般的です。
これらの仕事では源泉徴収票が発行されないため、自分で収入と経費を集計し、確定申告をする必要があります。
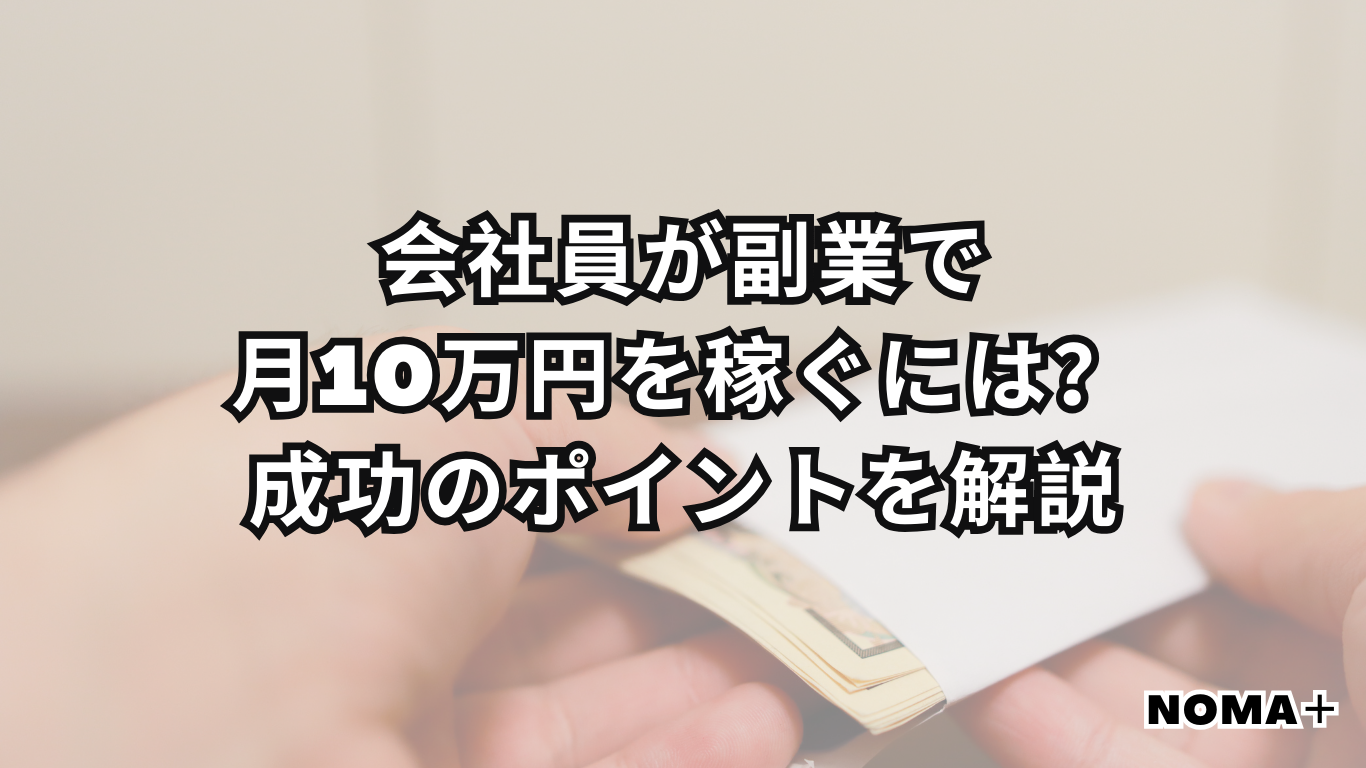
源泉徴収後の確定申告のやり方

本業で年末調整されていても副業は源泉徴収の状態なので、そのままだと納税は完了しません。本業の給与と副業の収入を合算し、正しい税額を計算するためには確定申告が必要です。
ここでは、確定申告が必要となる条件から、必要書類、具体的な申告方法まで流れを解説します。
確定申告が必要になる条件
副業をしている会社員は、本業以外の所得が「年間20万円を超える」と確定申告が必要になります。
ここでいう「所得」は、収入から経費を差し引いた金額を指します。同じ収入でも、所得が変わると確定申告の有無が変わるため、違いをしっかり理解しておきましょう。
例えば、副業の収入が30万円、経費が8万円の場合、所得は22万円となり、確定申告の対象です。一方、副業の収入が30万円、経費が15万円だった場合は、所得が15万円となるため確定申告をする必要はありません。
この「20万円ルール」は、給与所得や事業所得だけでなく、株式投資や不動産収入などの所得にも適用されます。
必要な書類
確定申告を行うには、1年間の収支がわかる書類が必要です。給与所得と事業所得・雑所得、源泉徴収の有無で用意するものが変わるので、自分には何が必要なのかを把握しておきましょう。
副業が給与所得の場合は、副業先から送られてくる源泉徴収票、本業の源泉徴収票の両方が必要です。本業と副業の収入を合算して申告します。
事業所得や雑所得の場合は、支払調書や請求書、収支を記録した帳簿、源泉徴収されている場合は源泉徴収票が必要です。確定申告に経費の領収書やレシートは使いませんが、保管義務があるため捨てずに保管しておきましょう。
株式や配当など投資による所得がある場合は、証券会社から交付される年間取引報告書が必要です。
申告方法
確定申告の提出方法は、大きく「e-Tax(電子申告)」と「紙の申告書を提出する方法」の2つに分けられます。
e-Taxは国税庁のシステムを利用してオンラインで申告する方法で、24時間いつでも手続きができ、還付金の振込も早いのがメリットです。マイナンバーカードやICカードリーダー、またはスマートフォンを使えば自宅から申告を完了できます。
紙での提出は、税務署に直接持参するか、郵送する方法です。パソコン操作に不安がある人や、物理的な書類で確認したい人に向いているものの、青色申告をする人にはおすすめできません。
どれを選ぶかは自由ですが、自分の環境や手間のかけ方に合わせて方法を選び、期限までに必ず提出しましょう。

確定申告をスムーズに終わらせる方法

確定申告は書類を集めて申告書を作成し、期限までに提出するというシンプルな流れですが、準備不足だと時間がかかり、提出間際に慌てる原因になります。
副業をしている会社員は、本業と副業の書類を整理して合算する必要があるため、効率的に進める工夫が欠かせません。ここでは、申告をスムーズに終えるための具体的なポイントを紹介します。
必要なものをそろえておく
確定申告をスムーズに行うために大切なのは、書類など必要なものを早めにそろえておくこと。
必要書類は所得の種類や仕事内容によって変わり、給与所得者の場合は本業と副業それぞれの源泉徴収票、雑所得・事業所得の場合は帳簿・支払調書・領収書などです。
医療費控除やふるさと納税を利用している場合は、その証明書類も一緒に準備しておくと安心です。また、e-Taxを利用する人はマイナンバーカードやICカードリーダー、ID・パスワードの作成も必要になってきます。
マイナンバーカードは管轄の役所、e-TaxのID・パスワードは管轄の税務署で発行できますよ。
確定申告書をスムーズに作成する方法
事業所得や雑所得がある場合、確定申告でもっとも手間取るのが「申告書の記入」です。スムーズに進めるためには、日々の収支をまとめておくことが何よりも大切。
領収書やレシートをため込まず、会計ソフトやアプリを使って毎月の売上や経費を入力しておけば、確定申告のときに計算する手間が省けます。会計ソフトは仕訳を自動化してくれるため、申告書の作成も効率的に行えますよ。
国税庁の「確定申告書等作成コーナー」と連携できるサービスも多く、転記の手間や計算ミスを防げるのも大きなメリットです。
確定申告の時期は年度末に当たるので、本業の種類によっては慌ただしくなります。心身の負担を減らすためにも、会計ソフトの導入をぜひ検討してみてください。
スケジュール管理のポイント
確定申告の期間は原則「2月16日〜3月15日」となり、この1か月間に書類の記入・提出を完了させなければなりません。
1月中に必要書類の確認を終え、2月に申告書を作成するなど、余裕を持ったスケジュールを立てることがスムーズに確定申告を終わらせるポイント。
帳簿づけがある人は、まとめてつけるのではなく「毎月」つけるようにしましょう。取引があるたびに帳簿をつければ、入力漏れがなくなります。
申告が集中する時期は確定申告会場や税務署が混み合い、質問や提出に時間がかかります。副業の場合は仕事が休みの日、帰宅後に確定申告を行うことになるので、24時間提出できる「e-Tax」を利用することで提出がスムーズになりますよ。

源泉徴収後の確定申告で注意すべき点

副業をすることで、確定申告を初めてする人もいるでしょう。確定申告は「1年間の所得を申告し、所得税を確定させるもの」なので、期限遅れは許されません。
また、所得を申告することで「税金」も変わってきます。ここからは、確定申告で特に気をつけたい3つのポイントを見ていきましょう。
申告期限を守る
確定申告の提出期限は、毎年2月16日〜3月15日までと定められています。この期限を過ぎてしまうと、延滞税や無申告加算税といったペナルティが課される可能性があります。
副業収入がある会社員は、本業の年末調整だけでは所得税を確定できません。確定申告をせずにいると「無申告」になり、本来より高い税金を払わなければならなくなります。
急な残業や急な用事が入り、予定がくるうこともあるので、確定申告は時間を見つけ「早め早め」に進めるようにしましょう。
副業により税金が増える
所得税と住民税は「前年の所得」を基に計算されるため、副業をして所得が増えれば自ずと税金も増えます。
所得税は、課税金額が高くなるほど税金も高くなる「累進課税制度」が採用されています。収入が増えたぶん余裕はできますが、「税金の支払いが増えたな…」と感じる瞬間が出てくるかもしれません。
また、副業が事業所得や不動産所得に当たる人は、副業の所得が290万円以上になると「個人事業税」が課せられます。所得が増えることはいいことばかりではない、ということも覚えておきましょう。
所得税が還付されるケースもある
副業で源泉徴収されている場合、確定申告を行うことで払い過ぎた税金が戻ってくることがあります。源泉徴収はあくまで概算で差し引かれているため、実際の所得税額より多く天引きされているケースがあるのです。
例えば、医療費控除や生命保険料控除、ふるさと納税などを利用している人は、確定申告をすることで差額が還付されます。
また、副業の収入が少なく、年間の所得税額が源泉徴収された額より低い場合も還付の対象です。確定申告は「追加の納税」だけでなく「税金を取り戻すチャンス」にもなるため、還付の可能性がある人は申告を忘れないようにしましょう。
まとめ|副業先から源泉徴収が届いたら、所得に応じて確定申告をしよう!
副業先から源泉徴収票が届くのは、「確定申告に必要だから」です。源泉徴収票は副業をするすべての人に届くわけではなく、源泉徴収票が届いても確定申告が不要な場合もあります。
確定申告が必要なのかどうかは、副業の所得が「20万円を超えているか」で判断しましょう。確定申告が必要な場合は、副業先から届いた源泉徴収票が必要です。
確定申告は提出期限を過ぎるとペナルティが発生します。トラブルを避けるためにも、スムーズな税務管理を心がけましょう。












コメント