会社員が副業をする際、気になるのが「確定申告は必要なのか?」という点です。この記事では、確定申告のやり方に加え、申告が必要になる条件、経費計上についても解説します。
確定申告を控えている人はもちろん、これから副業を始める人もぜひ参考にしてください。
会社員の副業に確定申告は必要?

副業を始めた会社員の方にとって、気になるのが「確定申告が必要かどうか」ではないでしょうか。本業の給与は年末調整で処理されますが、副業収入は条件によって申告が必要になります。
ここでは、副業の定義や確定申告が必要になる基準、そして年末調整との関係について解説します。
副業の定義
副業は、本業とは別に仕事をすることです。アルバイトやパートなどの給与収入、フリーランスとしての業務委託報酬やアフィリエイト収益、株式や配当、不動産収入なども副業の収入に該当します。
確定申告では、これらの収入は「給与所得」「事業所得」「雑所得」「不動産所得」などに区分され、それぞれに応じた申告方法が求められます。
「副業は関係ない」と思われがちですが、一定の年間所得を超えたら申告義務が発生するため、月の収入が少額であっても正しく理解することが大切です。
確定申告が必要になる金額の基準
副業をしている会社員の確定申告は、副業で得た所得によって必要かどうかが決まります。よく知られる「20万円ルール」は、副業の年間所得が20万円を超えると申告が必要になるというもの。
ここで注意したいのは、20万円の基準「収入」ではなく「所得」だという点です。所得は収入から必要経費を差し引いた額です。副業の収入が30万円あっても経費が15万円あれば所得は15万円となるので、申告する必要はありません。
ただし、住民税はこのルールは適用されないため、年間所得が20万円以下でも自治体への申告が必要です。
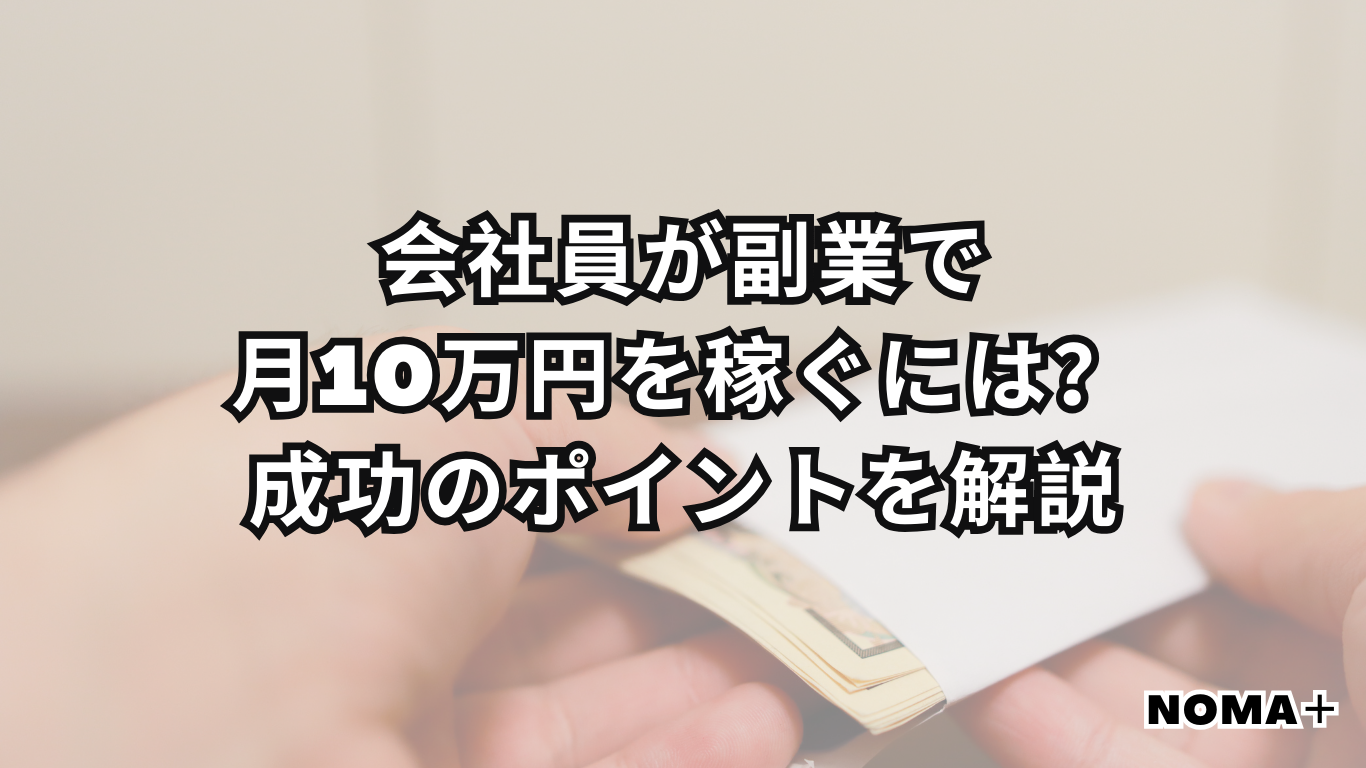
年末調整との違いと関係性
会社員の所得税は、毎月の給与から源泉徴収され、年末調整で過不足を調整します。年末調整は従業員の給与を対象としているため、副業で得た収入に対しては行われません。
給与所得を得ている会社員が副業で別の収入を得た際に確定申告を行うのは、副業で得た分の所得税を自分で納めなければならないからです。副業をして、その分の確定申告をしたとしても、給与にかかる所得税はこれまで通り勤め先で処理をしてもらえます。
「年末調整=本業の給与税務処理」「確定申告=副業や他の所得を含めた最終的な税務処理」と理解するとわかりやすいでしょう。
【所得区分別】副業で確定申告が必要なケース

副業とひと口にいっても、アルバイトやパートの給与収入、フリーランスとしての事業収入、ちょっとした副収入の雑所得、不動産や配当による所得などさまざまです。
所得の種類によって確定申告のやり方が若干変わるため、大まかな流れを把握しておきましょう。
給与所得(アルバイト・パート)の場合
会社員が本業以外にアルバイトやパートで給与を得ている場合、その収入も「給与所得」として扱われます。しかし、年末調整は1カ所でしか行えないため、副業の所得については確定申告しなくてはなりません。
アルバイトやパートの場合も、確定申告が必要になるのは「年間所得が20万円以上を超えたら」です。年末調整が終わると源泉徴収票をもらえるので、それを基に確定申告を行いましょう。
事業所得(フリーランス・アフィリエイト)の場合
フリーランスとして請け負った仕事の報酬や、アフィリエイト・広告収入などは「事業所得」に区分されます。
事業所得は収入から必要経費を差し引いた額で計算され、年間の所得が20万円を超える場合は確定申告が必要です。例えば、アフィリエイト収益が30万円、経費が5万円の場合、所得は25万円となり申告義務が生じます。
事業所得の申告は、年間の売り上げと経費を細かく記した「収支内訳書」もしくは「青色申告決算書」を提出しなくてはなりません。これらを作るためには毎月帳簿を付けなくてはなりませんが、青色申告を選択すれば最大65万円の特別控除を受けられますよ。
雑所得(副収入・小規模活動)の場合
副業による収入の中でも、規模が小さく事業として継続性が認められないものは「雑所得」に区分されます。代表例として、単発の講演料や原稿料、ポイントサイトやフリマアプリの利益、動画投稿や投げ銭による収益などがあります。
雑所得も事業所得と同じく、年間の収入から年間経費を引いた金額が20万円を超える場合に確定申告が必要です。なお、雑所得は青色申告の対象外となるため、事業所得のような特別控除は受けられません。
不動産所得・配当所得など特殊ケース
副業の中には、不動産収入や株式の配当収入など「特殊な所得」に当たるものもあります。いずれも、会社員の副業であれば「年間所得が20万円以上の場合」に確定申告が必要です。
不動産所得は、家賃収入から管理費や固定資産税などの必要経費を差し引いた金額で計算されます。赤字になった場合は損益通算が可能です。
配当所得は源泉徴収で納税が済んでいるケースもありますが、確定申告を行うことで配当控除を受けられる場合があります。複数の金融商品を運用している場合、申告方法の選択によって納税額が変わることもあるため注意しましょう。

副業所得が20万円以下でも確定申告したほうがよいケース

副業の年間所得が20万円以下であれば、原則として確定申告の義務はありません。しかし、申告をすることで控除を受けられたり、源泉徴収された税金が還付されたりする場合があります。
ここでは、20万円以下でも確定申告をしたほうがよい代表的なケースを解説します。
医療費控除や住宅ローン控除を受けたい場合
医療費控除や住宅ローン控除などを受けたい場合は、副業の年間所得が20万円以下であっても確定申告が必要です。
また、住宅ローンを利用してマイホームを購入した人は、初年度に確定申告を行うことで住宅ローン控除が適用されます。翌年以降は本業の年末調整に反映されるので、確定申告を行うのは基本的に初年度のみです。
「所得が少ないから関係ない」と思わず、控除対象がある場合は確定申告を積極的に行いましょう。
源泉徴収で払い過ぎた税金を還付したい場合
副業の種類や取引先によっては、報酬から源泉徴収しているケースがあります。たとえ年間の副業所得が20万円以下で確定申告の義務がなくても、そのままにしておくと払い過ぎた税金が戻ってきません。
確定申告をすれば、余分に支払った所得税が還付金として返金されます。「義務はないが、やったほうが得」という代表的なケースなので、報酬を受け取ったときに源泉徴収されているかを確認しておきましょう。
副業の確定申告のやり方【ステップ解説】

確定申告は難しく感じるかもしれませんが、流れを押さえればそれほど複雑ではありません。「申告書の作成」「必要書類の準備」「申告書の提出」という3つのステップに沿って進めるだけです。
ここでは、確定申告のやり方を手順に沿って解説します。
所得区分の確認と必要書類の準備
確定申告を始める前に、自分の収入がどの所得区分にあたるのかを確認し、それに応じた必要書類をそろえましょう。
アルバイトやパートであれば副業先から交付される「源泉徴収票」、フリーランスなら「請求書や帳簿、経費の領収書」、雑所得であれば「報酬明細や振込記録」などが必要です。不動産収入がある場合には、賃貸契約書や固定資産税の通知書なども準備しましょう。
所得区分によって確定申告書の作り方が変わってきます。確定申告をスムーズに進めるために、下準備をしっかりしておきましょう。
確定申告書を作成する
必要書類がそろったら、確定申告書を作成します。作成方法は、国税庁が提供する確定申告作成・提出システム「確定申告書等作成コーナー」、会計ソフト、手書きの3つです。
確定申告書等作成コーナーは、パソコンやスマホで確定申告書等作成コーナーのWebサイトにアクセスし、マイナンバーカード、または事前に作ったID・パスワードでログインします。
確定申告書等作成コーナーのメリットは、自動計算をしてくれること、e-Taxでの提出ができることです。地域ごとに設置される確定申告会場では、手書き作成のほか、確定申告書等作成コーナーでも申告書を作成できます(手書き作成の場合は郵送での提出となります)。
会計ソフトを使う場合は、事前に会計ソフトで確定申告書を作り、そのデータを確定申告書等作成コーナーにアップロードするのが一般的です。やり方は会計ソフトによって異なるため、しっかり確認しておきましょう。会計ソフトもパソコンとスマホの両方が使えますよ。
なお、青色申告は電子申告(e-Tax)をしないと65万円の特別控除を受けられません。手書きで申告書を作ると損をするので注意しましょう。

確定申告書を提出する
作成した確定申告書は、電子申告・郵送・窓口提出のいずれかで提出します。もっとも便利なのは「e-Tax」を使った電子申告で、マイナンバーカードやスマホを利用すれば24時間手続き可能です。
郵送は提出期限までに必着となるため、余裕を持って投函する必要があります。税務署窓口に直接持ち込むとその場で内容を確認してもらえるため、初めての人や不安がある人におすすめです。
どの方法を選んでも、提出期限は原則として申告する年の翌年2月16日〜3月15日までです。期限を過ぎるとペナルティが課せられるため、早めの提出を心がけましょう。
副業の確定申告で経費計上・青色申告はできる?
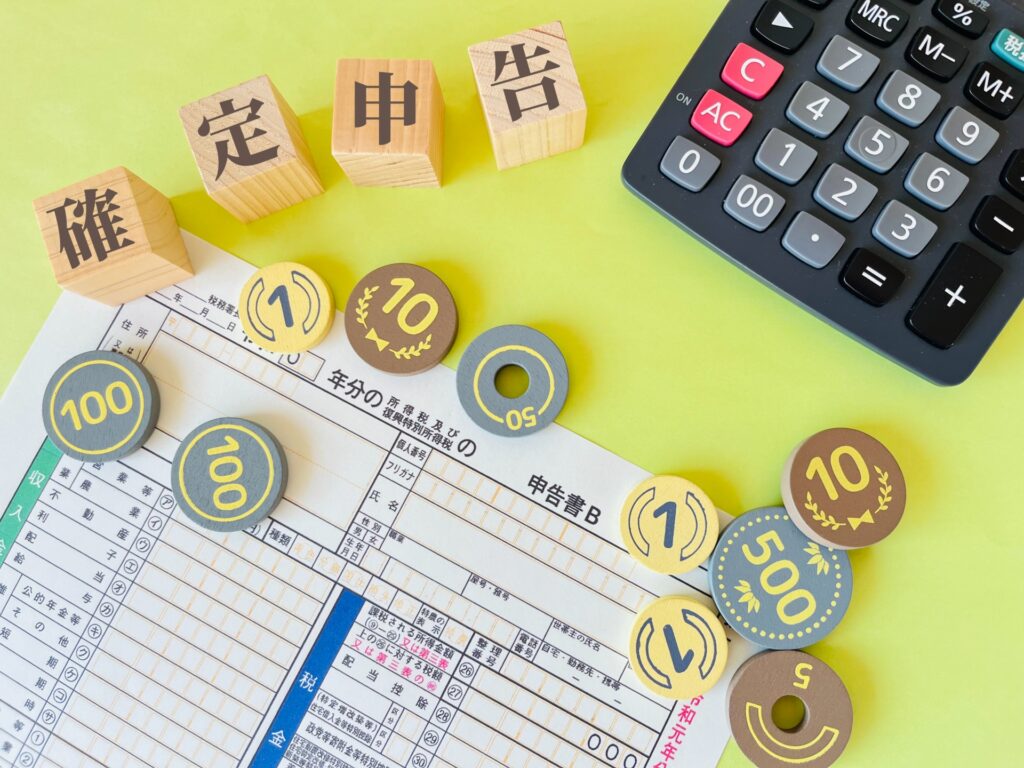
フリーランスで仕事を受けている場合、仕事にかかった経費は計上できるのか気になるのではないでしょうか。また、副業の収入が多い場合は「青色申告」ができるのかも疑問となるでしょう。
ここでは、経費計上の基本と青色申告の特徴について解説します。

経費にできる支出
副業で得た収入を確定申告する際、仕事に直接関係する支出を「必要経費」として差し引けます。仕事に直接関係する支出は、インターネットなどの通信費、業務に必要なパソコンやソフトの購入費用、電気代、家賃などです。
ただし、通信費や電気代、家賃のような私的利用と混在する支出は、事業用とプライベートようを按分(分ける)し、事業用でかかった分だけを計上します。
経費として認められるのは、電子・紙ともに「領収書があるもののみ」です。クレジットカードで支払ったものに関しては、利用明細でも認められるケースもあるため、なくさないように保管しておきましょう。
青色申告のメリットとデメリット
副業を事業として継続的に行っている場合、青色申告を選択できます。最大のメリットは「青色申告特別控除」で、複式簿記で帳簿をつけて電子申告をすれば最大65万円の控除が受けられます。
また、赤字を翌年以降に繰り越して黒字と相殺できる「損失の繰越控除」や、家族に支払う給与を必要経費として認められる制度を利用できるのもメリットです。
デメリットは、複雑な複式簿記を付けなくてはならないこと、領収書の管理に手間がかかること。簿記の知識がないという人は、AIシステムを搭載した電子帳簿法対応の会計ソフトを使うと効率良く管理できますよ。

確定申告をしなかった場合のリスク

副業で確定申告が必要なのに行わなかった場合、税金を納め忘れたという扱いとなり、ペナルティが課されます。さらに放置すれば税務署から指摘を受ける可能性もあり、結果として本来より多くの税負担を背負うことも。
ここでは、申告を怠った場合に生じるリスクを解説します。
延滞税が発生する
確定申告を期限までに行わず、納めるべき税金を遅れて支払った場合、「延滞税」が課されます。延滞税は納付期限の翌日から発生し、納付が遅れた日数に応じて利息のように加算される仕組みです。
一定期間内であれば年利7.3%か法定利率のいずれか低いほうが適用されますが、遅れが長引くとさらに高い利率がかかることもあります。
延滞税は本税とあわせて納付しなければならないため、余計な出費を防ぐために必ず期限内に申告・納税を済ませましょう。
無申告加算税が課される
確定申告をしなかった場合、税務署から指摘を受けて税額が確定すると「無申告加算税」が課されます。
これは本来納めるべき税金に上乗せして支払うペナルティで、原則として納付すべき税額の15%(50万円を超える部分は20%)が加算されます。
ただし、自主的に期限後申告をした場合や、税務署から指摘を受ける前に申告した場合には軽減措置があり、加算税を5%程度に抑えられることも。
いずれにしても、無申告のまま放置すれば余分な税金を支払うことになるので、期限を過ぎても放置せず、速やかに申告しましょう。
まとめ|会社員の副業も所得によっては確定申告が必要!
会社員が副業を行う場合、年間所得が20万円を超えれば原則として申告が必要です。確定申告は大きく「書類準備 → 作成 → 提出」の3順で進めるため、やり方はそこまで難しくありません。
青色申告・白色申告どちらで申告する場合も、給与以外で確定申告をする場合は収支をしっかり管理する必要があります。AI搭載の会計ソフトなどを使い、日々の帳簿付け、確定申告の書類作成をスムーズに進めましょう。












コメント