副業する会社員が確定申告をする際、「青色申告」と「白色申告」のどちらかを選ぶ必要があります。しかし、いざ選ぶとなると「自分は何色で申告したらいいんだろう…」と悩むのではないでしょうか。
この記事では、初心者にもわかりやすく青色・白色それぞれの特徴やメリット・デメリット、選び方のポイントを解説します。
副業する会社員の確定申告は何色が選べる?

会社員が副業をして確定申告を行う場合、選べるのは「青色申告」と「白色申告」の2種類です。
どちらも税務署に認められた正式な方法ですが、仕組みや得られる控除、必要な手間に違いがあります。それぞれの特徴を理解し、自分に合った申告方法を見極めましょう。
青色申告とは
青色申告は、「事業所得」「不動産所得」「山林所得」のいずれかで収入を得ている人が利用できる申告方法です。法人税の青色申告もありますが、この記事では個人の所得税に関する青色申告を紹介します。
青色申告は所得の種類が限定されていることに加え、事前に「青色申告承認申請書」を税務署へ提出する必要があります。
青色申告の特徴は、最大65万円の青色申告特別控除が受けられる、赤字を3年間繰り越せる、家族への給与を経費にできるなどの節税効果が期待できること。
副業でも青色申告を利用できますが、所得の種類によっては利用できない場合がある点に注意しましょう。
白色申告とは
白色申告は、青色申告の対象となる3つの所得区分に加え、給与所得・雑所得など青色申告対象外の所得区分の人も使える申告方法です。
青色申告のような事前申請はなく、提出書類も少ないものの、青色申告のような特別控除は受けられません。
青色申告が向いている人・白色申告が向いている人
青色申告が向いているのは、副業を継続的に行い、将来的に収入を増やしたい人です。控除や損失繰越といった節税効果を得られるため、経費が多く発生する人や規模が大きくなる見込みのある人にも有利です。
一方の白色申告は、副業を始めたばかりの収入が少ない人、申告の手間を最小限に抑えたい人に向いています。白色申告は青色申告に比べ、帳簿づけと確定申告がシンプルなので、簿記をやったことがない人にもおすすめです。

青色申告のメリットとデメリット

事業所得や不動産所得を得ている人は、青色申告が一番の選択肢となるかもしれません。特別控除は何よりの魅力ですが、デメリットも理解していないと選んだことを後悔するかもしれません。
ここでは、青色申告のメリットとデメリットを紹介します。
特別控除や損失繰越による節税効果
青色申告の最大の魅力は、節税につながる制度が充実していること。その代表たるものが「青色申告特別控除」です。
複式簿記に対応すれば55万円、さらに電子申告(e-Tax)や電子帳簿保存を行えば最大65万円を所得から控除されます。
このほか、30万円未満のパソコンや機材を一括で経費にできる「少額減価償却資産の特例」が使えたり、家事按分の割合が50%以下でも経費として認められるのも大きなメリット。
副業で赤字が出た場合は、最長3年間繰り越して翌年以降の所得と相殺も可能です。

複式簿記や帳簿保存の手間がある
青色申告最大のデメリットは、特別控除を受けるために「複式簿記」を使わなくてはならないことです。
複式簿記は、取引を「貸方」と「借方」に分けて仕訳帳や総勘定元帳に記録する記帳方法です。単式簿記に比べ複雑で、商業高校レベルの簿記知識がなければ仕訳でつまづく可能性があります。
確定申告では、確定申告書のほかに損益計算書・貸借対照表などの決算書を作成しなければなりません。さらに、帳簿や領収書、請求書などは7年間保存する義務があるので、慣れない人には負担となるでしょう。
白色申告のメリットとデメリット

白色申告は青色申告に比べシンプルなので、副業を始めたばかりの人におすすめです。しかし、そのシンプルさゆえのデメリットもあります。
ここでは、白色申告のメリットとデメリットを紹介します。
記帳や手続きが簡単
白色申告の最大の利点は、記帳や手続きが簡単なことです。事前に税務署へ申請する必要がなく、単式簿記で収入と支出を記録するだけで済みます。
単式簿記と聞くと難しそうに感じますが、単式簿記は「日付・項目・内容」「入金・出金・残高」を記録する家計簿のようなものなので、簿記をやったことがない人でも記入できます。
また、確定申告の必要書類も基本的に「収支内訳書」と「確定申告書」の2枚で済むのも大きな魅力です。
控除がなく節税効果が低い
白色申告のデメリットは、節税につながる制度がほとんどないことです。
青色申告では最大65万円の特別控除や赤字の繰越が認められますが、白色申告にはそれらがありません。そのため、所得が増えれば増えるほど税負担は重くなり、長期的に見ると不利になります。
また、30万円未満の資産を一括で経費にできる「少額減価償却資産の特例」ができず、家事按分の割合が50%以上でないと認められないなど、経費計上の幅が狭いのもデメリットです。
青色申告を利用する条件と必要な手続き

青色申告を利用するには、一定の条件を満たし、所定の手続きを行う必要があります。これを怠ると複式簿記で帳簿をつけても、e-Taxで確定申告をしても青色申告のメリットを得られません。
ここでは、青色申告を選べる人と手続きの仕方を解説します。
副業の所得が事業所得・不動産所得である
青色申告は事業所得・不動産所得・山林所得の確定申告に使える方法なので、会社員の副業では「事業所得」と「不動産所得」の人が中心となります。
フリーランスでWebライターやプログラマーなどの仕事を受けている場合は事業所得となり、マンションやアパートを貸して家賃収入を得ている場合は不動産所得として扱われます。
事業所得と判断される基準は、活動の継続性や規模、営利性です。ECサイトでの物販は雑所得とされるのが一般的ですが、定期的に販売やサービスを提供し、利益を出す仕組みを整えていれば事業所得と認められやすくなります。
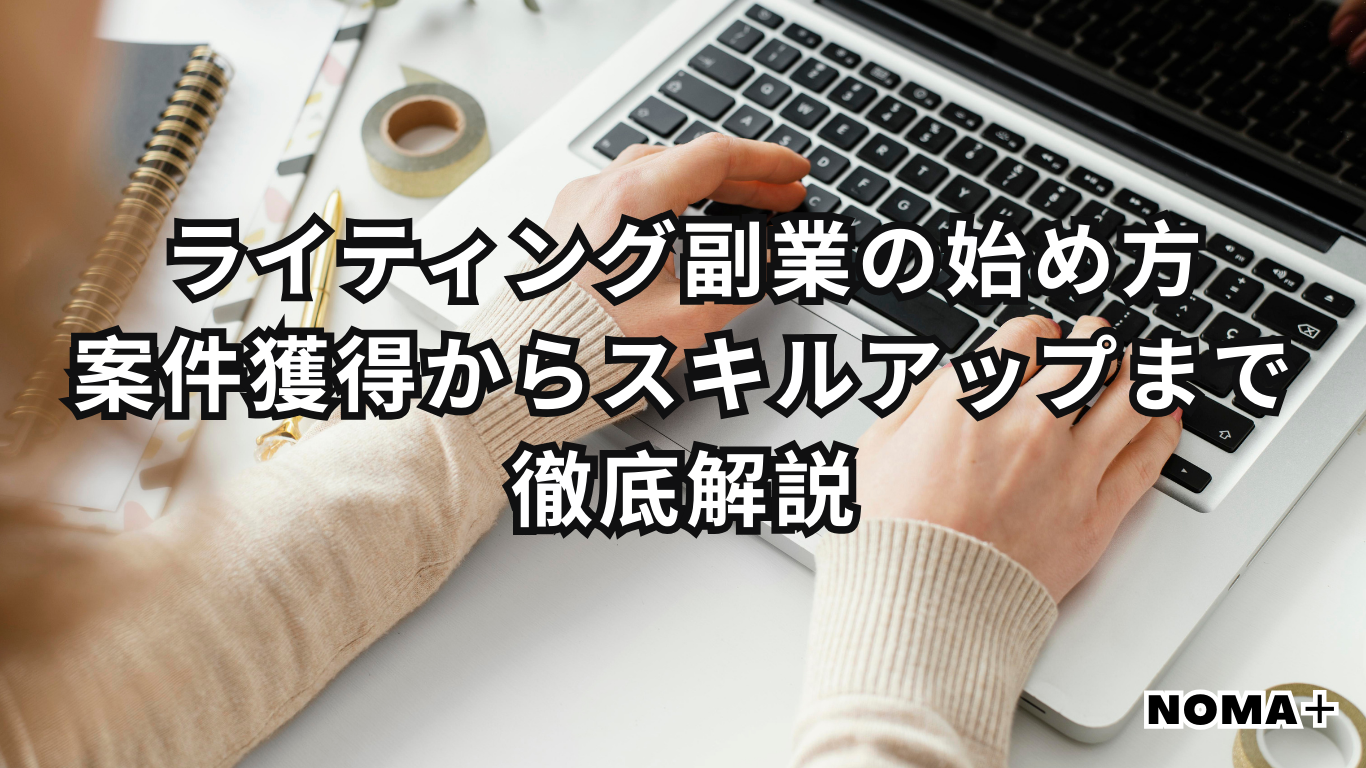
青色申告承認申請書の提出期限
青色申告を利用するには、税務署へ「青色申告承認申請書」を提出する必要があります。提出期限は原則「開業日から2か月以内」ですが、開業初年は白色申告、次年から青色申告にするのも可能です。
白色申告から青色申告に切り替える場合は、青色申告をしたい年の3月15日までに「青色申告承認申請書」を税務署に提出しましょう。
提出期限の「3月15日」は、確定申告の最終期限と同じ日です。確定申告をしたら申請するとすれば、機嫌を守りながら区切りをつけられますよ。
状況に応じて会計ソフトや税理士を利用する
青色申告は節税効果が大きい一方で、複式簿記や帳簿保存といった手間がかかります。記帳や仕訳に慣れていない人は、複雑な会計業務が入ることでより負担を感じやすくなるでしょう。
そこで役立つのが、AI機能搭載の会計ソフトや税理士のサポートです。会計ソフトを使えば、日々の取引を入力するだけで仕訳や決算書が自動作成され、電子申告にも対応できます。
取引が複雑化したり規模が大きくなった場合は、税理士に依頼することで安心して正確な申告が可能になります。なお、会計ソフトの利用料金、税理士の顧問料金は、どちらも経費計上できますよ。
\おすすめの会計ソフト/
副業する会社員の確定申告で何色にするか迷ったら

青色申告と白色申告にはそれぞれ特徴があり、どちらを選ぶべきかは副業の状況によって変わります。節税効果を重視するのか、手間を少なくしたいのか、あるいは将来的な副業の拡大を見据えるのか、自分がどうしたいのかを明確にしましょう。
ここでは、会社員が自分に合った申告方法を判断するための具体的な基準を紹介します。
副業の規模や収入額から選ぶ
申告方法を選ぶ際の大きな判断基準となるのが、副業の規模や収入額です。収入が少なく、経費もほとんど発生しないような小規模な副業であれば、白色申告で十分対応できます。
白色申告は、節税効果はないものの簡単で手間がないので帳簿をつける、経費を管理する、確定申告をするといった基本の流れを学べます。いきなり難しい青色申告をするよりも、会計業務に慣れてから移行したほうがよいでしょう。
一方、収入が多い場合は青色申告を選んだほうがお得です。特別控除や損失繰越を利用することで税負担を抑えられるため、一定以上の規模を見込める副業は早めに青色申告へ切り替えることをおすすめします。
将来的な副業の継続性・拡大性で選ぶ
確定申告の方法は、現在の収入規模だけでなく、将来的に副業をどの程度続けるかによっても選び方が変わります。副業を短期間しかやらない予定であれば、手間の少ない白色申告で十分です。
しかし、副業を長期的に継続し、収入を増やしていきたいと考えるなら、節税効果の高い青色申告が適しています。今後の副業をどうしていきたいのか、ライフプランに合わせて判断することが大切です。
まとめ|副業の確定申告を何色にするか迷ったときは、収入や規模で決めよう
副業する会社員の確定申告は、青色申告と白色申告のどちらでも行えます。ただし、青色申告は事業所得や不動産所得の人しか選べないため、給与所得や雑所得の場合は白色申告となってしまいます。
どちらも選べる状況にあり、何色にしようか迷う場合は、副業の収入や規模でどちらにするかを決めましょう。一時的なものでしかない場合は白色、継続する場合は青色がおすすめです。
どちらの方法で申告する際も、帳簿をつけなくてはなりません。AI機能搭載の会計ソフトを使えば、単式簿記はもちろん複式簿記もスムーズに入力できますよ。












コメント