会社員が副業を始めると気になるのが「経費はどこまで計上できるのか」と「確定申告が必要かどうか」です。
この記事では、副業の種類ごとに経費が認められるケース、経費にできる支出・できない支出、確定申告の基礎知識をわかりやすく解説します。
会社員の副業と確定申告の基礎知識

会社員が副業を始めると、収入によっては確定申告が必要になります。経費を計上して節税を狙うのであれば、確定申告のルールを正しく理解しておきましょう。
ここでは、「所得20万円ルール」や青色申告・白色申告の違いなど、確定申告の基本を解説します。

所得20万円ルールとは?
会社員が副業をしたからといって、必ず確定申告が必要になるわけではありません。自営業の人は年間所得が95万円以上ある場合に確定申告が必要になりますが、会社員は「年間所得20万円以上ある場合」です。
ここでのポイントは、20万円以上の基準が「所得」だということ。所得は、副業で得た収入から必要経費を差し引いた金額を指します。
そのため、副業の収入が50万円あっても経費が35万円あれば所得は15万円となり、確定申告は不要となります。
なお、年間所得は副業を始めてから1年間ではなく、「副業を始めた年の所得」です。10月1日から副業を始めた場合、その年の確定申告の対象になるのは10月1日〜12月31日の2か月分となるため注意しましょう。
青色申告と白色申告の違い
会社員が副業を行い、確定申告をする際、自営業の人と同じように「青色申告」と「白色申告」が選べます。白色申告は帳簿付けが比較的簡単で、誰でも利用できますが、節税メリットはほとんどありません。
一方の青色申告は、複式簿記による記帳の複雑さはあるものの、最大65万円の青色申告特別控除が受けられたり、赤字の繰越控除ができたり、家事按分の幅も広がります。
副業の規模が大きくなりそう、毎年一定の収入が見込めそうな場合は、青色申告を選んだほうが有利です。反対に、規模が小さく手間をかけたくないなら白色申告が現実的な選択肢となります。

赤字が出た場合の対応
経費が収入を上回り、赤字になるケースもあります。
赤字の場合は確定申告をしなくても問題ありませんが、青色申告を選択していれば「損益通算」といって本業の給与所得などと赤字を合算でき、所得税を減らせます。さらに、赤字を翌年以降3年間繰り越せる「繰越控除」も利用可能です。
一方、白色申告ではこれらの制度が使えず、赤字は翌年に持ち越せません。そのため、副業の規模がある程度大きく経費も多くかかる場合は、青色申告を選んだ方が有利です。
会社員の副業でも経費は計上できる?

確定申告書を作るには、副業で得た収入と、副業で使った経費が必要です。
「そこまで収入が多くないから」「本業が別にあるから」などの理由から、副業では経費計上ができないと考える人もいるかもしれません。
副業であっても経費計上は可能です。ここでは、どのような副業が経費計上の対象になるのか、経費となるもの、ならないものを解説します。
経費が認められる副業の種類
副業で経費を計上できるかどうかは、所得の区分によって異なります。
Webライターやデザイン、ネット販売などの業務委託や自営の仕事は「雑所得」や「事業所得」となり、必要経費を差し引いて申告できます。不動産収入があれば「不動産所得」として経費計上が可能です。
一方、アルバイトやパートなど給与が支払われる形態は「給与所得」に分類され、業務に関係するものを購入したとしても経費計上できません。
経費計上できるかどうかのポイントは、「雇われて得る収入」か「自分の責任で業務を行う収入」かです。給与所得の副業でも、年間所得が20万円以上ある場合は確定申告が必要になるので注意してくださいね。
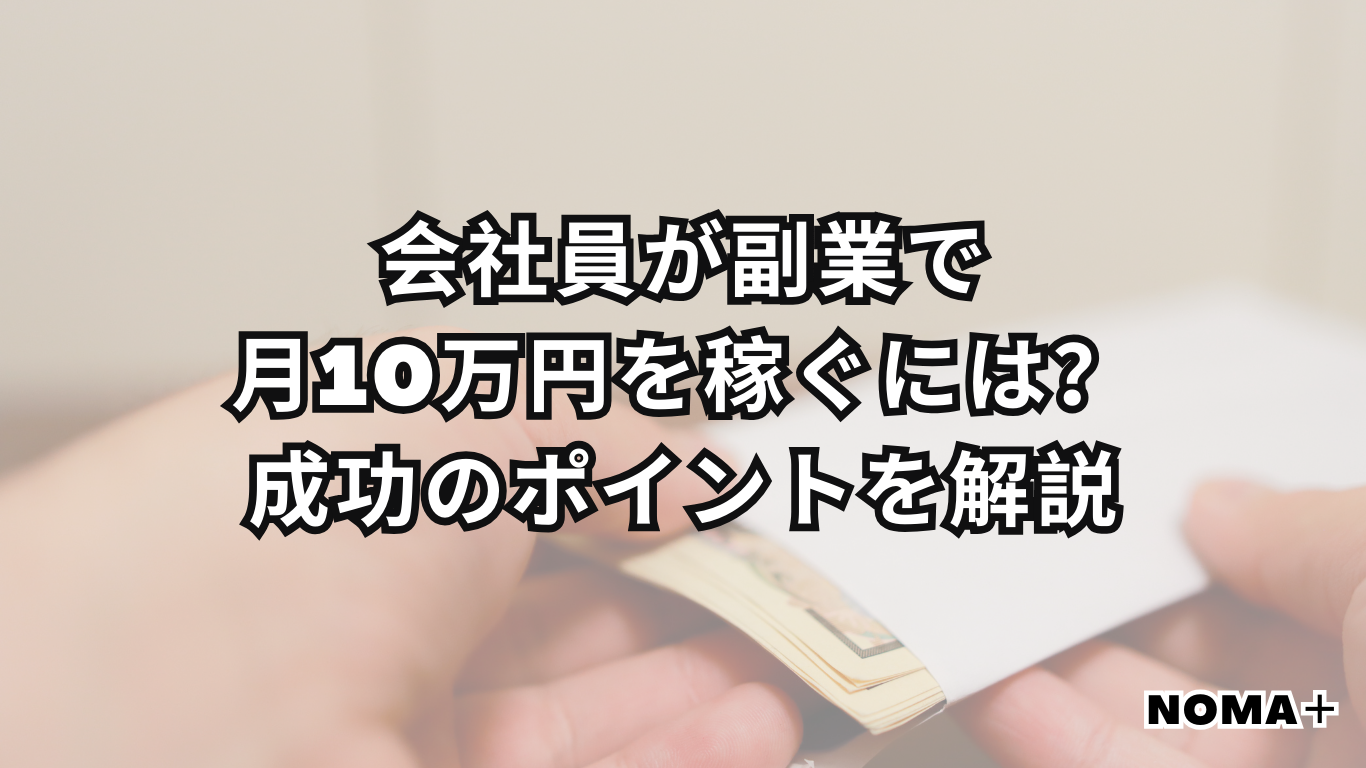
経費にできるもの
経費として計上できるのは、副業をする上で必要になるものです。この「必要になるもの」は幅が広く、会社員からすると「そんなものまで!?」と驚くようなものも含まれます。
確定申告を正しく行うために、何が経費になるのかをしっかり理解しておきましょう。具体的には次のような費用が対象になります。
- 家賃・光熱費・通信費の一部
-
自宅を作業場所として利用している場合は、仕事に使った割合を「家事按分」して計上できます。
- パソコン・プリンター・文房具などの備品や消耗品
-
副業の業務で使用するものは、購入費用を経費にできます。ただし、取得価額が10万円以上、かつ1年以上使用できる物に関しては減価償却が必要です。
- AIツールや会計ソフトなどの月額料金や購入費
-
業務をする上で必要なツールは経費になります。買い切りなのか、サブスクリプションなのかで勘定科目が変わるので注意しましょう。
- 交通費や打ち合わせでの飲食代
-
取材や顧客との打ち合わせなど、業務に関連する移動や接待費用は経費として認められます
経費にできないもの
自宅で行う副業はプライベートの線引きが難しくなります。水などの飲み物やメガネ、取材などに来ていくスーツ、トイレ・手洗いにかかる水道代は経費にできる・できないどちらだと思いますか?
正解は「経費にできない」です。先ほど挙げたものは本業でも関わりを持つので、自宅で副業をすれば仕事の一部のように感じます。しかし、これらは使用することで利益が出るわけではないので、経費とはなりません。
このほかにも、以下のようなものが経費とならないため注意しましょう。
- プライベートな支出
-
生活費や日用品、私用の外食費などは業務と関係がないもの。メガネ・スーツなどの衣装類もここに含まれます。
- 業務との関連性が不明な費用
-
副業に使ったことを説明できない費用、関連性が薄い費用は経費として認められません。
- 領収書がない支出
-
記録がない支出は原則として経費になりません。レシートや領収書を必ず保管しましょう。
- 治療費
-
眼精疲労や肩こり、腰痛、ケガなど、副業をする中で起こる身体の不調であっても、治療費は経費になりません。
経費にできるか迷ったときは、「副業の収入を得るために必要かどうか」を基準に判断しましょう。
領収書・レシートには保管期間がある!

副業で経費を計上した場合、領収書やレシートは必ず一定期間保存しなければなりません。白色申告では原則5年間、青色申告では帳簿とあわせて7年間の保存が必要です。
過去の領収書を数年間保管する理由は、確定申告が終わった後に税務署が内容を確認する(税務調査)場合があるから。確定申告をするときにあっても、税務調査のときにないと経費として認められないこともあります。
保存方法は、紙の領収書は紙のまま(原本のまま)でも、スキャンして電子データで管理しても構いません。電子データで受け取った領収書は、必ず電子データで保管しましょう。
青色申告をしている場合は、タイムスタンプを使用し、検索機能のある環境で保管しなくてはなりません。電子帳簿保存法についても理解を深めておきましょう。
経費の管理をラクにする方法

副業の経費は日々発生するため、正しく記録しておかないと集計が大変になります。本業と並行して管理できるように、効率的な方法を取り入れるのがおすすめです。
ここでは、経費管理をラクにする方法を紹介します。
クレジットカードや口座を副業用に分ける
副業の経費管理をスムーズに行うには、副業で使うお金とプライベートで使うお金を分けて管理するのが何よりの近道です。
副業専用のクレジットカードや銀行口座を用意しておけば、「なんの支払いだろう…」と悩むことがなく、帳簿への記入漏れもなくなります。クレジットカードで支払ったものは、内容によっては利用明細を領収書代わりにできますよ。
プライベートの支出が混在していると、業務に関係ない支出を経費計上するリスクが高くなります。税務署から指摘されると「知らなかった」では済まないため、経費管理をシンプルにしておくことが大切です。
\経費に使えるおすすめクレカ/
会計ソフトを使った効率的な管理
経費管理を効率化するには、AI機能を備えた会計ソフトを活用するのがおすすめです。
最近のクラウド会計ソフトは、銀行口座やクレジットカードと連携することで取引データを自動で取り込み、AIが内容を判別して勘定科目を提案してくれます。これにより仕訳や入力ミスが大幅に減り、経費管理がラクになりますよ。
また、過去の入力データを学習し、次回以降は自動で正しい仕訳を行うため、使うほど精度が高まるのも特徴です。
副業に充てられる時間が限られている会社員にとって、AIを活用した会計ソフトは作業を効率化する力強い味方になるでしょう。
\おすすめの会計ソフト/
領収書をなくしたときの対応
領収書を紛失すると、経費として認められなくなります。電子帳簿保存法では帳簿への入力を「2か月と7営業日までに」と定めているので、期限を過ぎる前に問題を解決しましょう。
まず、クレジットカードや銀行の利用明細、レシートのコピーなど、支出を証明できる資料を集めましょう。取引先や店舗によっては再発行に応じてもらえる場合もあります。
また、領収書がなくても「出金伝票」を作成し、支出内容・金額・日付を記録しておくことで、経費として認められるケースがあります。ただし、証拠書類が不十分だと否認されるリスクもあるため、紛失を防ぐことが第一です。
紙の領収書はファイルで整理し、スマホで撮影してクラウドに保存するなど、日頃からバックアップを取る習慣をつけておくと安心です。
まとめ|会社員の副業も経費計上をしっかりし、確定申告に備えよう
会社員の副業でも、条件を満たせば経費を計上して確定申告できます。副業の種類によって経費が認められるかどうかが変わり、必要経費にできるもの・できないものの区別も重要です。
帳簿に入力し、確定申告が終わっても、領収書は一定期間残しておかなくてはなりません。煩雑な管理を簡単かつ効率よくするには、AI機能を搭載した会計ソフトを使うのがおすすめです。
節税しつつ安心して副業を続けられるように、導入を検討してみてはいかがでしょうか。












コメント