仕事で役立つ資格を取得すれば、転職やキャリアアップの大きな後押しになります。しかし、すべての資格が同じように評価されるわけではありません。
この記事では、評価されやすいおすすめ資格10選を紹介します。自分に合った資格選びのポイントや勉強のコツも解説しますので、ぜひ参考にしてください。
仕事で役立つ資格とはどんなもの?

仕事で役立つ資格には、共通した特徴がいくつかあります。まず、実務に直結していることです。資格を持っていることで担当できる業務の幅が広がったり、専門性を証明できたりするものは高く評価されます。
次に、今後需要が高まる業界に関連する資格です。福祉や医療、ITなどの分野は今後も安定した需要が見込まれるため、資格を持っていればキャリアの選択肢が広がります。反対に、取得者が多すぎて差別化が難しい資格や、実務で活かす場面が限られる資格は、評価されにくい傾向があります。
おすすめ!キャリアアップにつながる資格10選

キャリアアップにつながる資格は、仕事や職種によって変わります。そのため、資格を選ぶときは「キャリアの方向性」に合わせることが大切です。ここでは、代表的な10個の資格と、それぞれの特徴を解説します。
1. 日商簿記検定
日商簿記検定は、企業の会計処理や財務状況の把握に必要な知識を証明できる資格です。2級以上を取得すると、実務に直結するスキルを持っていると評価されやすくなります。
経理や財務部門を目指す人に限らず、営業や企画の仕事でも数値に強い人材として信頼を得やすくなる点が強みです。また、上場企業や中小企業を問わず幅広い場面で活かせるため、転職市場でも安定した需要があります。
| 資格の種類 | 公的資格 |
| 難易度 | 2級:中級レベル、合格率20〜30%程度 |
| 主催者 | 日本商工会議所・各地商工会議所 |
| 受験料 | 2級:5,720円 |
| 試験実施回数 | 年3回(6月・11月・2月)、ネット試験(CBT方式)は随時 |
2. 宅地建物取引士(宅建)
宅地建物取引士(宅建)は、不動産取引の専門知識を証明できる国家資格です。不動産売買や賃貸契約の際に欠かせない重要事項の説明や、契約書類への記名押印など、法律で認められている独占業務を行います。
民法や宅建業法など幅広い法律知識が含まれるため学習量は多いですが、取得すれば不動産業界では必須資格として高く評価され、転職や就職活動において大きな武器になります。
| 資格の種類 | 国家資格 |
| 難易度 | 法律系資格の中では中級。合格率15〜18%程度 |
| 受験料 | 8,200円 |
| 試験実施回数 | 年1回(10月) |
3. 社会保険労務士(社労士)
社会保険労務士(社労士)は、人事や労務管理の分野で活躍できる国家資格です。労働法や社会保険制度に関する幅広い知識を備えていることから、企業の労務管理や社会保険手続きなどを担当できます。働き方改革や人材不足といった社会的な課題を背景に、近年需要が高まっています。
人事部門への転職や独立開業を目指す人にとって有力な選択肢となるほか、コンサルティング業務に携わることで企業の経営改善に貢献できる点も魅力。試験範囲が広く難易度も高いですが、合格すれば専門職として長く活躍できます。
| 資格の種類 | 国家資格 |
| 難易度 | 難関。合格率6〜7%程度。 |
| 受験料 | 15,000円 |
| 試験実施回数 | 年1回(8月) |
4. ファイナンシャルプランナー(FP技能士)
ファイナンシャルプランナー(FP)は、資産運用・保険・年金・税金など、暮らしに直結するお金の知識があることを証明できる資格です。国家資格の「FP技能士(1〜3級)」と、日本FP協会が認定する民間資格の「AFP・CFP」があり、いずれも金融業界や保険業界を中心に幅広い場面で評価されます。
FP技能士2級以上やAFP資格を取得していれば、実務に必要な知識を備えていると判断されやすく、転職やキャリアアップの際に大きな強みとなります。さらに、独立して相談業務を行う道も開けるなど、活躍の場が広い点も特徴です。
| FP技能士 | AFP・CFP | |
| 資格の種類 | 国家資格 | 民間資格 |
| 難易度 | 2級:合格率40〜50%程度 | AFP:FP2級合格+認定研修修了CFP:合格率15%前後の難関 |
| 主催者 | – | 日本FP協会 |
| 受験料 | 2級:学科4,500円、実技4,500円 | AFP:数万円〜(研修費+FP2級受験費用+AFP登録費用CFP:初回科目6,600円、2科目目以降1科目3,300円 |
| 試験実施回数 | 年3回(1月・5月・9月) | CFP:年2回(6月・11月) |
5. 介護福祉士
介護福祉士は、高齢者や障がい者に対して専門的な介護サービスを提供できる国家資格です。介護職の中で唯一の国家資格であり、資格を持つことで介護現場の専門性を証明できます。
介護人材の不足が続く中で需要は高く、転職や就職において大きな強みとなります。実務経験を積んだうえで取得するため、資格そのものが即戦力を意味する点も特徴です。
介護福祉士を取得すると、ケアマネジャーなど上位資格へのステップアップが可能となるため、福祉分野で長く活躍したい人に有益な資格です。
| 資格の種類 | 国家資格 |
| 難易度 | 中級。合格率70%前後(実務経験必須) |
| 受験料 | 18,380円 |
| 試験実施回数 | 年1回(1月) |
6. ケアマネジャー(介護支援専門員)
ケアマネジャー(介護支援専門員)は、要介護認定を受けた人のケアプランを作成し、介護サービス事業者や医療機関と連携して適切な支援をコーディネートする国家資格です。
介護現場で直接ケアを行う介護福祉士とは役割が異なり、ケアマネジャーは利用者や家族にとっての「相談窓口」となります。介護保険制度の中核を担う存在のため、高齢化が進む社会において高い需要があります。実務経験や関連資格が必要となることから難易度は高くなりますが、そのぶんキャリアアップが期待できますよ。
| 資格の種類 | 国家資格 |
| 難易度 | 中〜上級。合格率15〜20%前後 |
| 受験料 | 各自治体により異なる(おおむね10,000円前後) |
| 試験実施回数 | 年1回(10月頃) |
7. 基本情報技術者試験
基本情報技術者試験は、ITエンジニアの登竜門とされる国家資格です。プログラミング・アルゴリズム・ネットワーク・データベース・セキュリティといった幅広い基礎知識を問われるため、システム開発や運用に関わる業務の土台を固められます。
IT業界だけでなく、社内システムの運用やITリテラシーを必要とする一般企業でも評価される資格のため、転職やキャリアアップに有利に働きます。応用情報技術者試験など上位資格を視野に入れることで、専門性を高められますよ。
| 資格の種類 | 国家資格 |
| 難易度 | 初級〜中級。合格率25%前後 |
| 受験料 | 7,500円 |
| 試験実施回数 | 随時実施。全国の試験会場で受験可能 |
8. 中小企業診断士
中小企業診断士は、経営コンサルタントとして唯一の国家資格です。企業の経営課題を分析し、改善策を提案する力が証明できるため、経営企画やコンサルティング業務に携わりたい人に高く評価されます。
試験範囲は経済学・会計・経営法務・運営管理など幅広いため、難易度も高くなります。しかし、取得することで経営企画や管理部門でアピールできるだけでなく、将来コンサルタントとして独立する道も開けますよ。
| 資格の種類 | 国家資格 |
| 難易度 | 難関。一次試験・二次試験を突破、合格率4〜5%程度 |
| 受験料 | 一次試験:14,500円、二次試験:17,800円 |
| 試験実施回数 | 年1回(一次:8〜9月、二次:10〜11月) |
9. 電気主任技術者試験(電験三種・二種)
電気主任技術者試験(通称:電験)は、電気設備の保安監督を行うための国家資格です。電気事業法により、一定規模以上の事業用電気工作物には電気主任技術者を配置することが義務づけられています。そのため、電気主任技術者は電力会社や製造業、ビル管理業界などで欠かせない存在です。
第三種は受験資格がなく誰でも受験できますが、出題範囲が広いため計画的な学習が求められます。二種以上を取得すれば大規模な電気設備を扱えるようになり、キャリアアップや収入増が見込めます。
| 第三種電気主任技術者試験(電験三種) | 第二種電気主任技術者試験(電験二種) | |
| 資格の種類 | 国家資格 | 民間資格 |
| 難易度 | 難関。合格率10%前後 | 超難関。合格率5%前後 |
| 受験料 | インターネット申込7,700円、書面申込8,100円 | インターネット申込13,800円、書面申込14,200円 |
| 試験実施回数 | 年2回(上期・下期) | 年1回(9月) |
10. 登録販売者
登録販売者は、一般用医薬品(第2類・第3類)を販売できる資格で、ドラッグストアや薬局で幅広く活躍できます。薬剤師が不在でも医薬品を扱えるため、店舗運営には欠かせない存在です。
高齢化やセルフメディケーションの推進により市販薬の需要が伸びていることから、登録販売者の需要も拡大しています。受験資格に制限がなく挑戦しやすい一方で、第1類医薬品は扱えないなど制約もあり、合格には成分や作用、副作用に関する幅広い知識が求められます。
未経験から医療分野に関わりたい人におすすめの資格です。
| 資格の種類 | 公的資格 |
| 難易度 | 中級。合格率40〜50%前後 |
| 主催者 | 各都道府県・広域連合 |
| 受験料 | 都道府県により異なる(東京都は13,600円) |
| 試験実施回数 | 年1回(都道府県・ブロックごとに実施時期が異なる) |
\国家資格・民間資格/
国家資格と民間資格の違い

ファイナンシャルプランナーの「FP技能」と「AFP・CFP」のように、資格には国が定める国家資格と、民間の団体が独自に認定する民間資格があります。
それぞれの位置づけや役割を理解することで、自分のキャリアに合った資格を選びやすくなります。ここでは、国家資格と民間資格の違いを見ていきましょう。
国家資格の特徴
国家資格は、法律に基づいて国が認定する資格です。
医師・弁護士・教師・税理士・美容師・調理師などが代表例で、資格を持たなければ従事できない「独占業務」を伴うものも多く含まれます。どの資格も社会的信頼度が高いため、キャリアアップや転職に有利です。
国家資格は試験の内容や実施方法が法律で定められており、基準が一律に運用されています。また、受験資格も細かく定められています。大学や専門学校の卒業資格がなくても取得できる資格もありますが、代わりに実務経験が求められるケースもあるので注意が必要です。
民間資格の特徴
民間資格は、企業や業界団体などが独自に認定している資格です。国家資格とは違い、専門知識やスキルを持っていることを示す手段として活用されます。パソコン関連や語学、ビジネススキル系の資格などが多く見られます。
試験の内容や評価基準は主催団体が定めるため、同じような資格でも難易度が変わるのが特徴。受験資格の有無や学習に必要な期間も資格ごとに異なり、短期で取得できるものもあれば、一定の実務や講習を求めるものもあります。
受験勉強を始める前に、勤務先や業界で評価されるかを確認しておくと安心です。
民間資格でも仕事に役立つ?
民間資格は国家資格のように「資格がなければできない仕事」はありませんが、資格があることで業務の幅が広がります。IT系のスキルや語学力を示す資格は採用や配属の判断材料として評価されやすく、営業や事務といった幅広い職種で活かせる資格は日常業務の効率化や専門性のアピールにつながりますよ。
しかし、民間資格は数が多く、知名度や信頼性に差があるのも事実です。勤務先や応募先で評価されているかどうかを事前に確認し、自分のキャリアプランに合った資格を選ぶことが大切です。
自分に合った資格の選び方
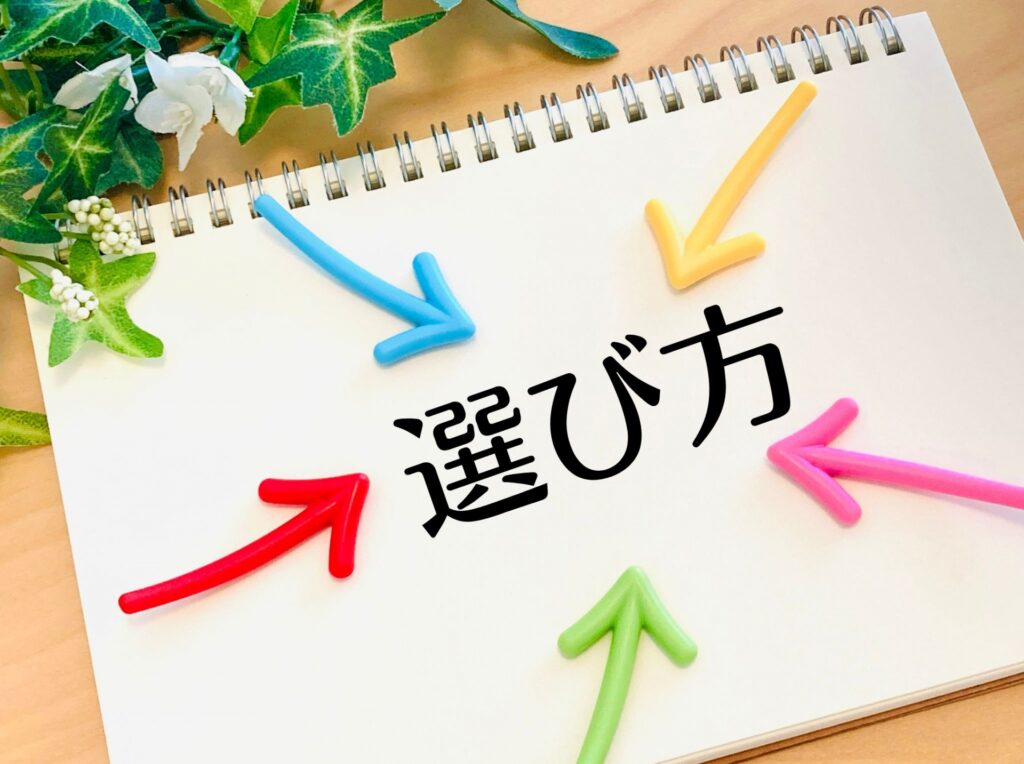
仕事に活かせる資格は国家資格・民間資格を合わせると数が多いので、どれを選ぶか迷う人もいるのではないでしょうか。時間やお金をかけて学ぶのであれば、自分のキャリアやライフプランにしっかり結びつく資格を選ぶことが大切です。ここでは、資格選びの際に意識したい3つのポイントを紹介します。
キャリアの方向性や希望職種から逆算する
資格を選ぶときは、まず自分がどのようなキャリアを歩みたいのかを明確にしましょう。例えば、経理や会計の分野で専門性を高めたいなら簿記や税理士を、労務管理に携わりたいなら社会保険労務士を目指すといったように、希望する職種から逆算して必要な資格を考えるのが効率的です。
1級・2級など等級のある資格は、等級によって評価が変わります。せっかく資格を取っても評価されなければ意味がないため、その業界で必須とされる資格や評価されやすい資格を等級も含めてチェックしておきましょう。
興味・適性・強みを活かせる資格を探す
資格取得には長期的な学習や試験対策が必要になるため、自分の興味や適性に合った分野を選ぶことが大切です。関心のある分野であれば学習を続けやすく、知識も実務に結びつきやすくなります。興味のない分野を選んでしまうと学習が負担になり、挫折する可能性が高くなります。
自分の強みを活かせる資格を選ぶことも、キャリアアップには効果的です。コミュニケーション力が高い人ならキャリアコンサルタントや営業関連資格、論理的思考力を活かしたいなら会計系資格など、自分の得意分野に合わせてキャリアプランを立ててみてはいかがでしょうか。
費用・学習期間・難易度を比較して選ぶ
資格取得には、受験料のほかに教材費や講座費用などがかかります。学習期間も資格ごとに変わるため、時間や費用をどのくらいかけられるか考えましょう。
また、資格には実務経験が受験資格として求められる場合や、基礎知識がなければ学習のハードルが高くなる資格もあります。時間や費用と一緒に、自分の実力や経験に見合っているかどうかも確認しましょう。
初めから難易度の高い資格を目指しても、スキルが見合っていなければ合格する確率が下がります。「最終的にこれを取りたい」と決め、まずは3級そして2級など、堅実に進めていきましょう。
【スタイル別】資格試験勉強のポイント

資格試験の勉強方法には大きく分けて「独学」と「通信講座」があります。どちらにもメリットと注意点があり、自分の学習スタイルや生活リズムに合った方法を選ぶことが合格への近道です。ここでは、それぞれの勉強法のポイントを紹介します。
独学で勉強する場合のポイント
独学のメリットは費用を抑えられることです。市販の教材や過去問題集を活用すれば必要最低限のコストで学習を進められますが、自己管理ができないと身にならなかったり、継続できなかったりします。
独学で進める場合は、まず試験範囲を把握し、日ごとの学習時間や進捗を管理できるスケジュールを組みましょう。過去問題を繰り返し解くことで出題傾向をつかみ、理解が不十分な箇所を重点的に復習すると効率良く学習できます。
通信講座で勉強する場合のポイント
通信講座は、カリキュラムがあらかじめ組まれており、教材やオンライン講義、添削課題などを通じて体系的に学べるのが特徴です。サポートを受けながら学習できるので、勉強の進め方で迷いやすい人や、質疑応答をしたい人に向いています。
しかし、受講料が発生するため、独学に比べコストが高くなる点に注意。資格取得というゴールは同じでも、講義の内容や教材、受講期間は講座によって変わります。
内容を重視するか金額を重視するかは人それぞれなので、複数の講座を比較し自分に合ったものを選ぶようにしましょう。
まとめ|仕事で役立つ資格を取得する際は自分に合った勉強方法で学習しよう
資格はキャリアアップや転職の強い味方になりますが、評価される資格とそうでない資格があるため、「将来どのように働きたいか」をイメージして選ぶことが重要です。
国家資格であれ民間資格であれ、自分のキャリアに直結するものを選べば評価の対象となります。資格を取得するには勉強が必要になるため、勉強方法も自分に合ったものを選ぶことが大切です。
ぜひこの機会に、資格を取得してみましょう。
\国家資格・民間資格/












コメント