副業の収入が一定額を超えた場合、会社員であっても確定申告が必要になります。副業をやっている人の中には、会社員の副業でも青色申告が使えるのか疑問に感じている人もいるのではないでしょうか。
この記事では、青色申告の仕組みやメリット、切り替えるタイミングを解説します。青色申告の注意点も解説しますので、ぜひ参考にしてください。
会社員の副業も青色申告を選べる!
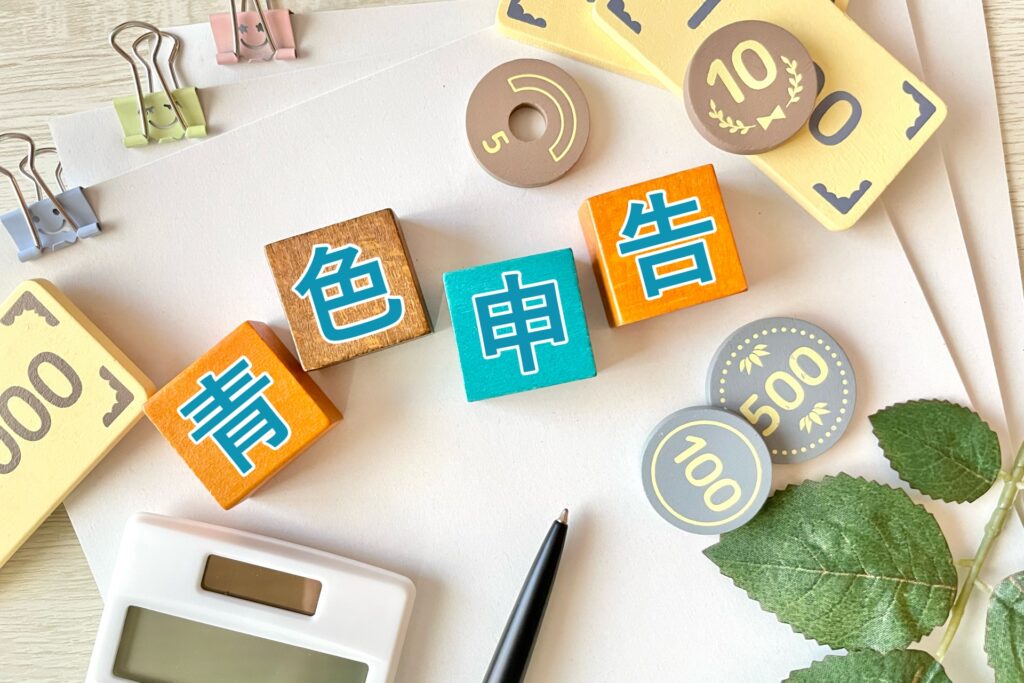
副業の確定申告でも青色申告を選べますが、副業の種類によっては選べないケースもあります。はじめに、青色申告の仕組みや白色申告との違い、青色申告ができる副業の種類を見てみましょう。
そもそも青色申告とは?
青色申告は確定申告の方法のひとつで、生業として事業を営む人のほか、副業で事業をする人も利用できます。
青色申告の大きな特徴は、事前に「青色申告承認申請書」を税務署へ提出しなくてはならないこと。また、青色申告は原則「複式簿記」で帳簿をつけなくてはなりません。それにより、確定申告では貸借対照表や損益計算書なども提出します。
白色申告は事前申告がいらず、帳簿も「単式簿記」で問題ありません。どちらを選ぶかは事業者の自由ですが、事業の大きさに合わせて選ぶのがおすすめです。
青色申告ができる副業の種類
青色申告はすべての副業に適用できるわけではありません。主な対象は「事業所得」と「不動産所得」になり、パートやアルバイトなどの「給与所得」は対象外です。
フリーランスとして請負業務を行う、ネットショップを運営する、アフィリエイトやコンテンツ制作で継続的に収入を得ている場合は、事業所得として扱われます。マンションやアパートなど、不動産を貸し出している場合は不動産所得です。
一方で、株やFXの利益は譲渡所得や雑所得に分類されるため青色申告は選べません。自分の副業がどの所得区分に該当するかを確認することが、正しく申告するための第一歩です。

副業の確定申告で青色申告を選ぶメリット
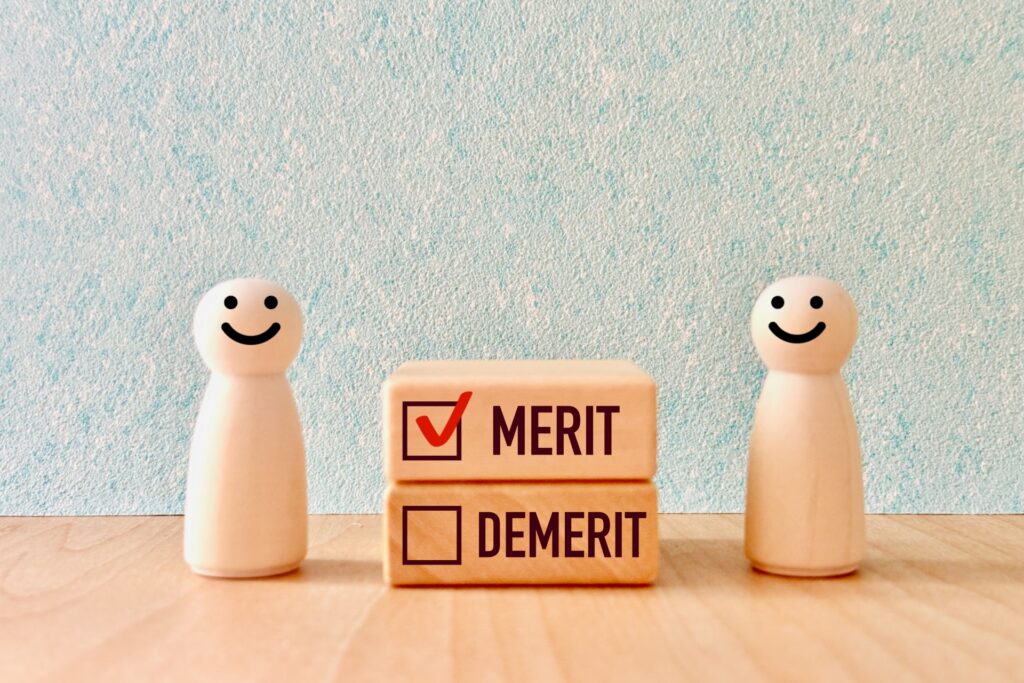
会社員が副業で確定申告をする際、青色申告を選ぶことでさまざまなメリットが得られます。代表的なのは、特別控除による節税効果や赤字の繰り越し制度です。
ここでは、副業だからこそ知っておきたい青色申告の具体的なメリットを紹介します。
青色申告特別控除で節税効果を得られる
青色申告の最大の魅力は「青色申告特別控除」を受けられることです。
複式簿記で帳簿をつけ、e-Taxで申告するなどの条件を満たせば、最大65万円の控除を受けられます。単式簿記でも10万円控除が適用されるため、白色申告よりも節税効果は大きくなりますよ。
所得税が課税されるのは「収入から経費を引いた所得」です。青色申告特別控除はここから65万円または10万円差し引かれるので、控除を受けることで課税所得が減り、所得税・住民税を減らせます。

赤字を翌年以降に繰り越せる
青色申告では、副業で赤字が出た際の金額を最大3年間繰り越せます(繰越損失)。初年度に設備投資などで赤字になった場合、翌年以降の黒字から赤字分を差し引くことで税を軽減できます。
繰越損失は事業所得・不動産所得・譲渡所得・山林所得での赤字にのみ対応しており、雑所得には使用できません。
また、青色申告では損益通算も認められており、同じ年に発生した他の所得(本業の給与所得)と赤字を相殺することも可能です。副業と本業、2つの収入源を持つ会社員にとって、損益通算は大きなメリットとなるでしょう。
家事按分で経費計上の幅が広がる
確定申告では、副業で得た収入と一緒に事業に関連する支出(経費)を申告しなくてはなりません。
経費計上は副業でも認められていますが、家賃や光熱費、通信費など「プライベートと共有するもの」に関しては、事業で使用した分だけが経費と認められます。
どこまでが事業で、どこまでがプライベートかを分けることを「家事按分」といい、青色申告では比率が50%以下であっても経費計上が可能です(白色申告は50%以上が条件)。
正当な理由がない、割合が異常に高い家事按分は税務調査の対象となる可能性があるので、何でもかんでも経費にするのはやめましょう。
青色申告の条件と確定申告の仕方
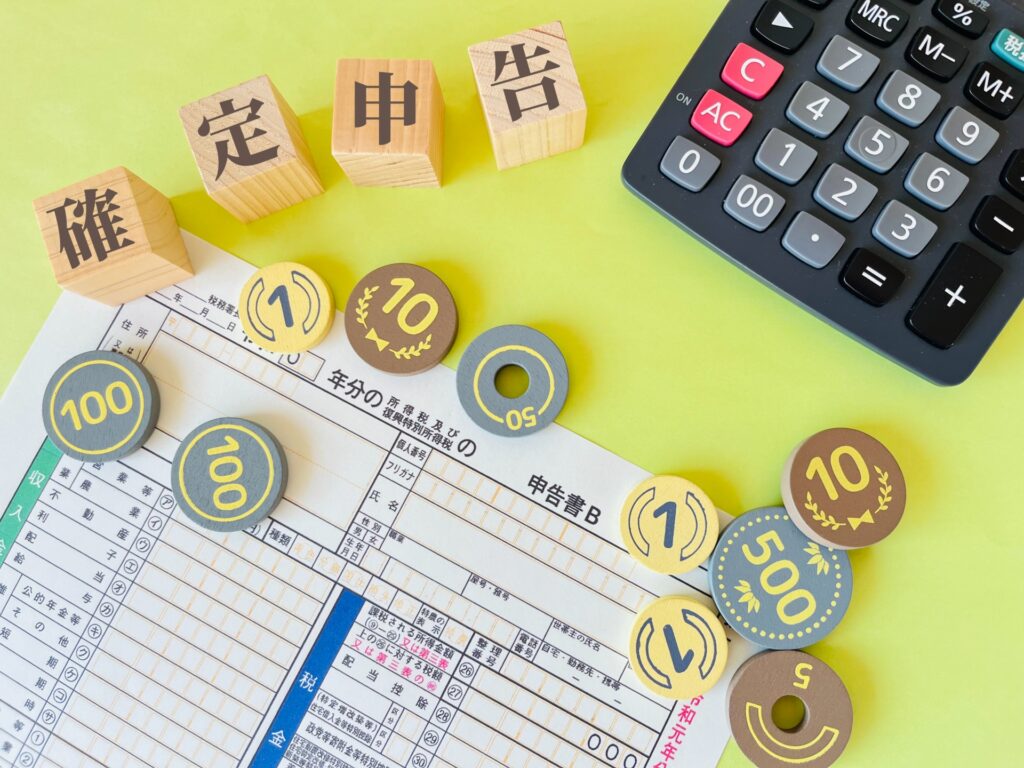
青色申告を利用するには、事前の申請や一定の要件を満たす必要があります。利用条件を知らずにいると、青色申告が利用できなかったり、恩恵を受けられなかったりします。
ここでは、会社員が副業で青色申告を行うために必要な手続きと条件を紹介しますので、青色申告を希望する方は参考にしてください。
開業届と青色申告承認申請書の提出が必要
副業で青色申告をするには、「青色申告承認申請書」に加え「個人事業の開業・廃業等届出書(開業届)」の提出が必要です。開業届は税務署に事業を始めることを申告する手続きで、副業であっても原則として必要になります。
青色申告承認申請書と開業届は、どちらも管轄の税務署へ提出します。青色申告承認申請書は開業から2か月以内の提出が原則ですが、2か月を過ぎても提出は可能です。
ただし、3月15日以降に提出すると青色申告は「翌年から」になるので、提出のタイミングだけ気をつけましょう。
帳簿付けと書類の保存義務がある
青色申告を行うには、日々の取引を帳簿に正しく記録し、領収書や請求書などの証拠書類を保存しなくてはなりません。
青色申告では「複式簿記」と「単式簿記」の両方が選べ、複式簿記で記帳することで最大65万円の特別控除、単式簿記の場合は10万円の控除が受けられます。
仕訳帳をはじめとした帳簿類、経費の領収書は、7年間保存しなくてはなりません。7年間の間に帳簿や領収書を紛失するとペナルティが課せられるので、紛失しないよう厳重に管理しましょう。
確定申告の期限と手続きの流れ
青色申告・白色申告に関係なく、確定申告期限は毎年3月15日です。前年の1月〜12月までの収支を帳簿にまとめ、決算書や確定申告書を作成して税務署へ提出します。
副業の場合は本業の給与と合わせて申告する必要があるため、本業の勤め先から渡される源泉徴収票も忘れずに用意しましょう。
確定申告書を作成したら、e-Taxまたは郵送、税務署窓口へ持参して提出します。65万円の青色申告特別控除を受けるには電子申告が必須なので、必ずe-Taxを利用しましょう。
3月15日の期限を過ぎると、延滞税や加算税の対象になる可能性があります。「しまった」とならないよう、余裕を持って準備しておきましょう。

青色申告で副業の確定申告する際の注意点

青色申告には節税効果などのメリットがある一方で、注意すべき点もあります。特に帳簿付けの手間や申告期限を守らなければならない点は、多くの会社員にとって負担となりやすい部分です。
ここでは、副業で青色申告を行う際に押さえておきたい注意点を紹介します。
複式簿記による記帳の手間がある
青色申告で最大65万円の特別控除を受けるためには、複式簿記による帳簿付けが必須です。
複式簿記は収入と支出を両方の勘定に記録するため、取引の流れを正確に把握できますが、その分作業は複雑で時間もかかります。
また、10万円以上の機材や備品などは原則として「減価償却」が必要です。減価償却は複式簿記の中でも複雑で、償却し終わるのに数年かかります。最低限の簿記の知識が求められるので、人によっては記帳作業が大きな負担となるかもしれません。
65万円の特別控除には条件がある
青色申告特別控除の中で、最大の節税効果を得られるのが「65万円控除」です。会社員の副業でも利用できますが、そのためには以下の条件を満たす必要があります。
- 青色申告承認申請書を事前に提出する
-
申請をしなければ青色申告を利用できません。開業から2か月以内、またはその年の3月15日までに提出しましょう。
- 事業所得または事業的規模の不動産所得である
-
副業がアルバイトや雑所得の場合は対象外です。事業としての継続性を認められる必要があります。
- 複式簿記で帳簿をつけ、貸借対照表・損益計算書を作成すること
-
単式簿記は65万円控除の対象外です。また、正確な記帳も求められます。
- 発生主義で帳簿をつけている
-
発生主義は、取引が生じた時点で記帳する方法です。現金の動きで記帳する現金主義で青色申告をするには条件があり、それを満たした上で事前申請しなくてはなりません。
- 電子帳簿法に適用している
-
e-Taxでの申告や優良な電子帳簿に保存するなど、電子帳簿法で定められた要件を満たす必要があります。
- 確定申告を期限内(原則3月15日まで)に提出する
-
申告が遅れれば控除は無効になり、延滞税や加算税の対象になる可能性があります。
青色申告は「事前準備」が何よりも大切です。条件を確認し、確定申告のベースを整えておきましょう。
副業の確定申告を青色申告にするタイミング

青色申告は節税効果が大きい一方、帳簿付けや申請などの手間も伴います。そのため、副業を始めたばかりの人には向いていません。では、どのような状況になったら青色申告を検討すべきなのでしょうか。
ここでは、会社員が副業で青色申告を選ぶべき具体的なタイミングを紹介します。
副業収入が20万円を超えたとき
会社員の場合、副業の年間所得が20万円を超えると確定申告が必要になります。所得は「収入から経費を引いた金額」なので、副業収入が30万円でも、必要経費を差し引いた所得が18万円であれば申告義務はありません。
青色申告は青色申告承認申請書を提出したり、複式簿記で帳簿をつけたりと、白色申告に比べ面倒です。年間所得が20万円以上にならなさそうな場合は、様子見として1年間は白色申告を選んでもよいでしょう。
副業が継続的に利益を出し始めたとき
副業の収入が単発ではなく、継続して利益を生むようになったときも、青色申告に切り替える大きなタイミングです。
毎月安定して売上が立つ、あるいは年間を通して黒字が見込める場合は「事業所得」として扱われるため、青色申告を利用する最初のハードルを超えられます。
この段階で青色申告を選択すれば、特別控除による節税効果だけでなく、赤字が出た際の繰り越し制度も活用でき、長期的な収支の安定につながります。副業が本格化してきたと感じたら、青色申告への移行を視野に入れましょう。

青色申告での確定申告をスムーズにする方法

青色申告は節税効果が大きい反面、帳簿作成や書類管理の負担が課題になります。そこで役立つのが、会計ソフトやAI機能を活用した効率化です。
ここでは、青色申告をスムーズに進めるための具体的な方法を紹介します。
会計ソフトを使って仕訳をする
青色申告の大きな負担のひとつが、日々の帳簿付けです。複式簿記のルールに従って手作業で記録するのは時間がかかり、初心者にとっては間違いのリスクも高まります。
そこで有効なのが「会計ソフト」の利用です。銀行口座やクレジットカードと連携すれば取引データを自動で取り込み、仕訳まで自動処理してくれます。また、確定申告に必要な決算書や申告書も自動で作成されるため、手間を大幅に減らせますよ。
\おすすめの会計ソフト/
AI機能で経費計上や仕訳の効率を高める
近年の会計ソフトには、仕訳や経費計上の精度を高めるAI機能が搭載されています。
例えば、同じ支出が繰り返される場合、AIが自動で勘定科目を学習し、次回以降は自動仕訳してくれます。領収書をスマホで撮影すると文字を読み取り、勘定科目を自動判別して帳簿に反映する便利な機能が付いている会計ソフトもありますよ。
AI機能を活用することで記帳のミスが減り、帳簿にかかる時間も短縮できます。副業と本業を両立する会社員にとって、AIは青色申告をサポートする相棒になるでしょう。
まとめ|副業が軌道に乗ってきたら、青色申告で確定申告をしよう!
会社員の副業でも、事業所得や不動産所得として認められる場合は青色申告を選べます。
最大65万円の特別控除や繰越損失、損益通算などのメリットはあるものの、複式簿記で記帳したり、事前に青色申告承認申請書を提出したりと、面倒なこともあります。
青色申告への切り替えは、継続して利益が出始めたタイミングがおすすめです。財務管理の手間を減らすために、AI機能搭載の会計ソフトを取り入れてみましょう。

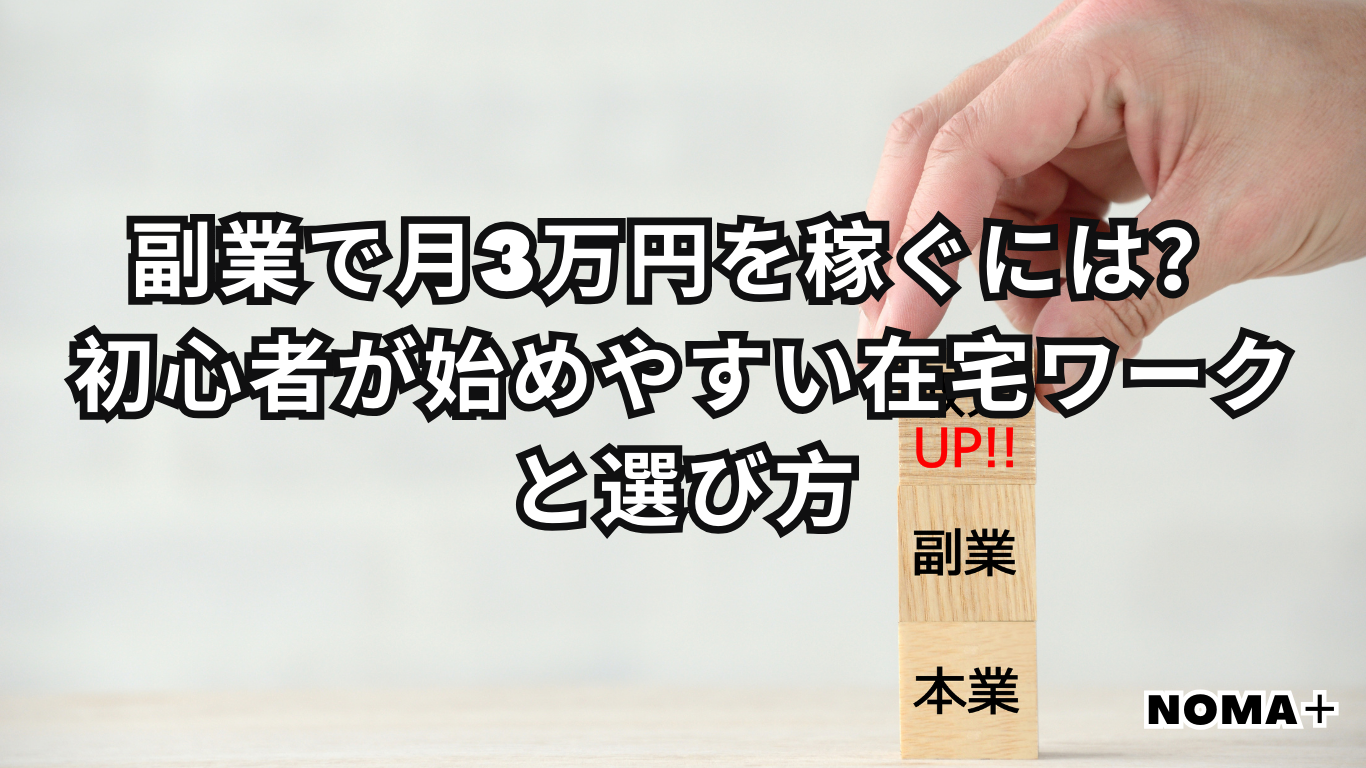











コメント